「1年間で早稲田慶應に受かるのは無理!!」
多くの人はそのように考えるでしょう。
もちろん、生はなんかな努力で合格することはできませんが、
適切な努力、勉強法を積むことで合格することは可能です。
本ブログ記事では、どのようにして1年間で早稲田慶應に合格していくのかの
スケジュール例と参考書をお伝えしていきます。
ページ目次
早稲田慶應の配点を考える

まず一番大事なのは、配点です。
テストというと得意な科目で点を取ると、
考えてしまいがちですが、
これは最後の手段です。
どの科目に力をいれて、勉強をしていくのかは志望大学の配点から考える必要があります。
早慶の配点をみると・・
まずは下記を見てください。
| 大学学部 | 英語点数 | 数学点数 | 理科2科目 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田理工学部 | 120点 | 120点 | 120点 | 360点 |
| 慶應理工学部 | 150点 | 150点 | 200点 | 500点 |
※志望の学科によって若干点数が異なるので注意してください。
どちらも英語と数学でそれぞれ30%以上で二つ合わせて、
60%以上を占めていることがわかります。
理系の人は多くは数学ができますので、
数学ではなかなか差がつきづらいです。
ではどこで差がつくのか?
理系は実は、英語で差がつきます。
理系も英語ができないと合格は難しい

理系だから数学と理科ができれば合格できますよね?英語が苦手だからできる限りやりたくないんですが・・
![]()
![]()
理系でも英語は大事ですよ。
上述の通り、理系であっても英語ができないと合格は難しい。
なぜ理系で英語は重要なのか
科学技術で最先端を進んでいるのは、言わずもがなアメリカです。ある分野で最先端または、ある程度深い議論の文献を読みたい!となった時に、
英語を使うことは必要不可欠になります。
また、学会での発表も英語で行うことも多いので、
実は文系以上に理系では英語を使う必要があるのです。
そのため、英語は重要なのです。
理系は英語が苦手な人が多い・・・
これまで理系の受験生も数多く見てきていますが、
理系の受験生の多くが英語を苦手としています。
それはなぜでしょうか。
なぜ理系で英語嫌いが多いのか?

色々と理由があると思うのですが、
- 覚えることが多い
- 数学や理科ほど勉強の仕方が明確でない
- 文章が文系の文章ばかりで興味がない
このようなところが理由になると思います。
覚えることが多くて英語の勉強に気が進まないというタイプの受験生は、
動機づけの部分で失敗してしまっているので、
英語以外の科目もできてない可能性が高いです。
高いレベルまでの勉強の仕方がわからない・・・というタイプの受験生は、
本記事でも英語については説明していきますが、下記の記事で詳しく英語の勉強法について詳しく勉強しています。

- 【何からはじめたらいい?という人向け】
【まず始めることをお伝えします】 - 早慶に合格するための戦略とは?
合格するための戦略とは? - 【高1】早慶現役合格の勉強法を徹底解説
志望校に合格するためにやるべきこと紹介 - 【高2】現役で早慶GMARCHに合格
必要な勉強法(勉強時間、参考書)を紹介 - 【高2】早慶絶対合格!!のためにすること
勉強時間、スケジュール、参考書、勉強法の紹介 - 早慶満点者インタビュー
早慶圧勝のために具体的に何をしたら良いのか
1年で早慶を目指すのに重要なこと

理系受験生が軽視しがちな英語の重要性をわかってもらった上で、
理系において1年間で合格するための勉強法を見ていきましょう。
合格の肝は、
夏までにいかに数学と英語の基礎を固めることができるかどうかということです。
勉強ができるようになるための鉄則として、
やることを絞ってその部分を何度も繰り返すということです。
特に理系の場合は、4科目もあり色々と大変になるのですが、
できない段階において4科目も一気にやっていくのは得策ではありません。
そのため最初の段階では、英語数学と絞ってください。
*もちろん、理科を勉強しないわけではありませんが、
英語数学の基礎学力の低さに応じて、英語と数学への優先度を高めてください。
数ⅢCを早く終わらせることができるかが鍵
英語が重要なのは、先ほど述べた通りですが、
理系ですから数学ももちろん重要です
すなわち、数3までをいかに早く終わらせることができるかも重要になってきます。
理系の数学で数学3が出ない大学はないと言っていいでしょう。
数学3の問題はどちらかと言うと計算が大変なだけで、パターン化のしやすい問題が多いです。
習ってできるようになれば、できるようになるのですが、
ですが、そこに至るまでの道は、
わかっていなくてはいけない前提条件が多くて、大変です。
高校3年生から、数学1から全部やり直す。。となるとかなり大変です。
早めの段階で、先取りをしてできるようにしていきましょう。
数学ⅢCの基礎固めをしたい!
![]()
このような場合は、下記で具体的な参考書を紹介していますので確認してください。
数学の勉強法全体についてはこちらの記事で説明しています。

- 早慶合格のための塾の選び方とは?
学習塾のタイプごとに塾を説明 - オンラインで早慶合格を目指せる塾の比較
1,2年生から合格するための戦略を立てるには? - 集団と個別のメリットデメリット比較
集団、個別に合う合わないは存在します - 【コーチング塾】早慶に合格できない?
コーチング塾の裏事情を暴露 - 【暴露】参考書ルート学習の落とし穴
参考書だけでは合格できないわけとは?
理系早慶志望の1年間のスケジュール

ここから、4月時点の成績別にどのようにスケジュールを組んでいったら良いのかをお伝えします。
理系で1年で早慶合格を目指すスケジュール
文系受験生で1年間でスケジュールを組んでいくにあたって下記の成績別で見ていきます。
- 偏差値55-60程度
- 偏差値50程度
- 偏差値30-40程度
当塾では偏差値の換算については、河合塾のデータを使っています。
成績データについては、河合塾のホームページから見ることができるので、興味がある人はこちらから参照してください。
それぞれ偏差値ごとに、
5月→8月→11月と模試がある月までに
どのようなことをすれば良いのかというのと、
直前期にすることをお伝えしていきます。
下記がスタート時点での偏差値と季節ごとにどの程度成績を取っておけば良いのかの目安資料となります。

◆以下から自分の偏差値を選択し、1年間の合格スケジュールを確認しよう
1.偏差値55~60の方はこちら
2.偏差値50の方はこちら
3.差値30~40の方はこち
偏差値55-60からの早慶合格


4月の段階でこの偏差値がある生徒は、
勉強の仕方次第で早慶合格の可能性がかなり高い生徒になります。
そのため、どのように1年間ハンドリングをしていくかが非常に重要になってくるのです。
このレベルの学生の注意点
- 数学は偏差値70を超える
- 英語で偏差値65を切らないように!
- 理科は苦手分野を作らないようにする
5月までのスケジュール

記述模試での目標偏差値
- 数学:偏差値65
- 英語:偏差値60
- 理科:偏差値55
5月の数学の模試の戦略
まずは数学でどのくらいの点数を取るのかを考えてみましょう。
数学の偏差値65というと、
点数で言うと大体130点程度取れているイメージになります。
問題の割合で言うと、毎年同じではないですが、
大体下記のような分野から出題されています。
- 1,小問集合40点分、
- 2,確率・整数(40点)
- 3,数学2(ベクトル、図形)から80点
- 4,数学ⅢC(微積・複素数選択)で40点
取らなくてはいけない優先度で考えると、
小問集合→数学ⅢC→数学Ⅱ分野ですね。
先ほども述べていますが、兎にも角にも理系の数学は、
数学ⅢCまでを速く習熟できているかどうかにかかっています。
現時点で数学ⅢCも含めた模試で偏差値55-60ある場合は、
数学ⅢCの精度を上げていくのと、数学2での苦手部分を強化していきましょう。
必要な数学の参考書は?
計算力を高めるドリルとして合格る計算シリーズは必須です。
基礎問題精講で数学3までの基礎を確認ができるのでやっていくと良いでしょう。
基礎問題精講シリーズで演習量が足りない・・という分野については、
チャート、フォーカスゴールド、レジェンドといった網羅系の参考書をやっていってください。
5月の英語の模試の戦略
続いて英語の模試の戦略を考えていきましょう。
英語の偏差値60というと、
大体110点程度取れている換算になります。
この110点というのは、長文2つで両方とも40点程度で、
作文パートで20点、文法で10-20点取ることで可能です。
得点の割合として、、、
- 長文→80点
- 作文→20点
- 文法→10-20点
上記の割合で取っていくことができれば良いでしょう。
英語の偏差値60以上を取るためのポイントは?
大きく点数を占めるのが長文となります。
内容一致はもちろんこと、
偏差値60近くをとるためには下記事項の理解が必要です。
和訳問題、代名詞の見分け、
理系文章の読み方、単語の理解が必要
この辺りを理解することが必要になってくるでしょう。
もちろん、長文だけができればいいわけではありません!
多くの受験生が手薄になりがちな、
英作文・整序英作文でも
高得点を取れるように学習していく必要があります。
最近は、英検を早い段階から受けることが多いためか、
自由英作文は点数を取ることが多いのですが、
整序英作文で点数を取ることが難しい傾向があります。
もちろん、この問題を解くためには熟語、構文把握力が必要です。
加えて、整序問題の対策を積んでおくこともお勧めします。
必要な英語の参考書は?
■読解問題
もしこれまでにパラグラフリーディングの基礎を学んでいない場合は、
入試長文を読むためのパラグラフ・リーディング 高校上級用 25 (発展30日完成シリーズ)を読んでおくと良いでしょう。
英語で高い成績を取るためにはパラグラフリーディングの理解が必要です。
パラグラフリーディングというと、
そのようなテクニック的な読み方があると思い込んでいる人が多いのですが、、
そうでありません。
英語ができる人の普通の読み方です。
ネイティブはパラグラフという塊で理解をしており、
ライティングの際も厳格なルールで行なっています。
そのため、パラグラフで理解をしていない=英語ができないということを早い段階で理解をしておきましょう。
その他、英語長文の読み方として、『ぐんぐん読める英語長文Standard』関正生の『The Rules英語長文問題集3入試難関 (大学入試)』があるのでおすすめです。
『ぐんぐん読める英語長文Standard』
The Rules英語長文問題集3入試難関
精読も重要
偏差値55~60程度の学生の場合、
単語力もそれなりにあって読むことに苦はないのですが、
比較や倒置、省略、といった部分の処理が苦手です。
特に比較の理解ができてない場合が多いので、この部分を強化できる精読の教材をやっていくと良いでしょう。
そのような場合は『英文熟考・下』がおすすめです。
英検準1級も6月で習得できるように・・

英検を習得していると受験をものすごく有利に進めることが可能です。
早稲田慶應に合格する人であっても滑り止めと言われるランクの大学は必要です。
もちろんあった方が良いのですが、、、
SCBTを利用して8月までに合格できない場合は、
あとはどうしても立教!・・・と言う場合でない限りは、
諦めても良いでしょう。
英検準1級の勉強の仕方についてはこちらの記事で説明しています。
理系の場合は準1はもってなくても良い?
理系の場合は、文系ほど英検が有利になるケースがないのですが、英単語を覚えるという目的で英検を覚えると良いでしょう。慶應理工は最近難しい単語が答えになるケースが多く、早稲田も少なくても英検準1レベルの単語がわからないと内容が理解し難いです。
他の科目は?

■物理・化学・生物
力をいれるのは、数学・英語と言っても理科ノータッチはいけません。
できれば、夏前までに各科目1通り理解をしておいたほうが良いです。
もし時間がなければ、
化学は理論、
物理は力学、電磁気、生物は生物基礎まででも構いません。
現役生の場合は学校の授業の範囲と模試に合わせて勉強をしておけば良いでしょう!
![]()
必要な参考書は?
物理であれば「秘伝の物理」シリーズが動画講義もありていねいでわかりやすいです。
アウトプットで入門問題精講を使うと良いでしょう。
化学、生物については基礎問題精講で問題ないです。
8月までのスケジュール

記述模試での目標偏差値
- 英語:偏差値65
- 数学:偏差値65以上
- 理科:偏差値60
上記が目指すべく偏差値となるでしょう。
■数学
自分が苦手な分野の基礎問題、
応用レベルの参考書を使って入試レベルの問題を解いていきましょう。
おすすめの参考書は「1対1対応の演習」です。
■英語
これまで行なってきたことに加えて、
引き続き音読を続けることによる長文の理解をすることがありますが、
さらに倒置や省略といった少々難解な構文が出てくるので追加での参考書が必要となります。
英検を習得しておくことが、入試を有利に進めていくには必要不可欠です。
早慶志望であれば、英検準一級を習得できるように早めの対策をしておきましょう。
■理科科目
英語数学の基礎が固まったら、
徐々に理科科目の演習も増やしていきましょう。
理科科目の演習ができるかどうかが重要になってきます。
必要な参考書は?
■物理、化学、生物
物理については、引き続き秘伝の物理を行いつつ、
「基礎問題精講」「秘伝の物理」問題集をやって基本問題の復習をしていくと良いでしょう。
化学については、
基礎問題精講の内容を再度確認しつつ、重要問題集、新標準問題演習で演習量を増やしていくと良いでしょう。
生物についても同様で、基礎問題精講を行いつつ、重要問題集をやっておく形で良いでしょう。
11月までのスケジュール

記述模試での目標偏差値
- 数学:偏差値70
- 英語:偏差値70以上
- 理科:偏差値65
理科はこれまでの進路によっては最後まで苦戦する人もいるかもしれません。
ですが、焦ってはいけません。
対策によっては最後まで上げることは全然可能ですので、
過去問と問題集を何度もやっていきながら、行うようにしましょう。
直前期のスケジュール

過去問中心で勉強を進めてください。
過去問の使い方については、こちらのYoutubeでも伝えています。
偏差値50からの早慶合格スケジュール


続いて、一番多い層である偏差値50の層を考えてみましょう。
このレベルの学生の注意点
- 偏差値60以降で勉強法の転換ができるか
- 数学、英語をいかに無駄なく勉強ができるか
- 理科の苦手をなくすこと
5月までのスケジュール

記述模試での目標偏差値
- 数学:偏差値55-60
- 英語:偏差値55-60
- 理科:偏差値50
5月の模試の戦略
まずは、数学を考えていきましょう。
数学の模試は、下記範囲から出題が予想されます。
- 小問集合40点分、
- 確率・整数(40点)
- 数学Ⅱ(ベクトル、図形)から80点
- 数学ⅢC(微積・複素数選択)で40点
偏差値、55というと100点前後が目標になるでしょう。
点数を狙っていく分野は、最初の小問集合と、数学3分野でしょう。
数学ⅢC分野については、
とりあえずどちらかに絞っても問題ありません。
まずは自分が得意!と思える分野、部分を数学3で作っておくと、
これまでの復習もできるので効率的です。
偏差値55~60を狙うとなると、そこ+alphaで点数をとっていくと言うイメージ感になるでしょう。
続いて、英語で考えると
難易度が一番オーソドックスな河合塾の模試で考えてみましょう。
記述で英語の偏差値60というと、
大体115-120点程度の点数があれば、この偏差値が取れます。
この115-20点というのは、長文2つで両方とも35点程度で、
作文パートで15-20点、文法で10-20点取ることで可能です。
得点の割合として、、、
- 長文→70-75点
- 作文→15-20点
- 文法→10-20点
英語で偏差値60を取る上で重要なことは?
この学力の生徒が圧倒的に足りてないことは英単語力です。
初期段階においては、英単語力=英語力ですので、
英単語を覚えるのにまずは時間を割いてください。
英単語を覚えられない=英語ができないということにつながってしまいます。
覚え方については、こちらのブログ記事などを参考にして頑張って覚えてください。
続いて重要なのは、構文把握力です。
構文を把握することができないと、和訳がメチャクチャになってしまいます。
和訳は点数配分が大きいので、
ここで点数を落とす=模試で点数が出ないということになってしまいます。
なので、4月段階で偏差値50程度の人は、
英単語力と構文把握を鍛えて、並行して長文を読んでいくと良いでしょう。
構文把握についてはこちらの記事をご覧ください
長文の読み方についてはこちらの記事をご覧ください
他の科目は?
他の科目よりも数学ⅢCまでが終わってない場合は数学、
続いて英語に重点を置いて勉強をしてください。
そのほかの科目は、
難しい問題は良いので入門問題精講レベルの基本問題のみで夏までに、
各科目、大体の大枠で理解をしておきましょう。
このレベルの教材を何度も行って、基本問題・概念の理解を行うのが重要です。
必要な参考書は?
■数学
計算力を高めるための教材として合格る計算シリーズをやって、無意識でもできるようにしてください。
数学の基本問題については、
1A2Bの復習で文系の数学 重要事項完全習得編をやってください。
3については、大学入試 数学III おさえておきたい基礎50+応用50が良いでしょう。
1A2Bの量が足らない場合はチャートやおさえておきたいシリーズの1A2Bをやると良いでしょう。
■英語
精読については英文熟考・上をしっかり理解をしてできるようにしてもらうことで、精読の基礎学力は完成です。
英文法については、桐原1000かDual Effectあたりの網羅系の英文法の問題集をマスターしてもらうと良いでしょう。
単語帳については、ターゲット1900、LEAP、システム英単語のどれか基本的な英単語帳をやってもらうと良いでしょう。
その他基本単語帳についてはこちらの記事で記載しています。
■理科
8月までのスケジュール

記述模試での目標偏差値
- 数学:偏差値65
- 英語:偏差値60
- 理科:偏差値50
数学の偏差値も上げるのは結構難しいのですが、、、
重要なのは、計算力と基礎問題のパターン処理能力です。
この問題、なんか見たことあるのだけれど・・・
最後まで導出できない。というのではダメです。
持っている教材に載っている問題の全てを解き切れるようにすること、
また、日本語で導出までを説明できるようにしてください。
計算力についても結構みんな疎かにしがちなのですが、
毎日計算問題集をやるようにするのが、合格への近道です。
また英語の偏差値は60あたりから、上げるのは難しくなってきます。
とはいえ適切な勉強をすることで、成績を上げることは可能です。
結論から言うと、勉強の仕方を変えることができてないからです。
偏差値60から上に上げる勉強はこれまで通りの勉強をしていてもできることはできません。
英語のロジックを理解しないと、一気に成績を上げることは不可能です。
偏差値60から70に上げるためには、
パラグラフの理解と論構造を理解していくことができなければ、
成績を上げることはできません。
英語の得点の割合はどうすれば良いのか?
英語の記述模試で点数を取るためには、
- 長文→80-90点
- 作文→20-30点
- 文法→10-20点
上記の割合で取っていくことができれば良いでしょう。
必要な参考書は?
■数学
基本的にはこれまでやったことの定着が最優先です。
ここまで行って数学が得意であれば、
『1対1対応の数学』シリーズを行ってもらって、
難しいようであれば『大学入試 森本将英の 理系数学』をやってみると良いでしょう。
数学が苦手な分野があるようであれば、坂田先生のシリーズや数学のとりせつをやってください。
■英語
上述の通り、長文で点数を取れるかどうかが、ポイントになるでしょう。
必要な教材も長文の教材です。
上述の通り、長文で点数を取れるかどうかが、ポイントになるでしょう。
もしこれまでにパラグラフリーディングの基礎を学んでいない場合は、
入試長文を読むためのパラグラフ・リーディング 高校上級用 25 (発展30日完成シリーズ)を読んでおくと良いでしょう。
その他、英語長文の読み方として、『ぐんぐん読める英語長文Standard』関正生の『The Rules英語長文問題集3入試難関 (大学入試)』があるのでおすすめです。
『ぐんぐん読める英語長文Standard』
The Rules英語長文問題集3入試難関
読む際のポイントをまとめた書として『The Essentials』も読んでいくのが良いでしょう。
できれば、この時期に英文熟考・下もやっておきたいです。
■理科
インプットは、引き続き同じ教材で。
11月までのスケジュール

記述模試での目標偏差値
- 数学:偏差値70
- 英語:偏差値65
- 理科:偏差値60
数学英語をここまで鍛えることができたら、
あとは理科をいかに仕上げていくことができるかが鍵となります。
直前期のスケジュール

直前期については、理科やこれまでの問題を暗記科目中心の勉強になると思います。
上述の成績が取れているようであれば、
過去問で苦手部分を発見して、
なぜできてないのかを考えてそれをメモして見返すようにしていきましょう。
偏差値30からの早慶合格スケジュール


このレベルから1年で早慶に合格するのは相当大変です。
かなりの努力をしないと受かることはできないと言うことを認識しましょう。
ですが、適切な努力をすることができれば合格することは可能です。
このレベルの学生の注意点
1,英語への苦手意識をどうするか
2,数学の処理能力を上げるためには
3,理科インプットに偏らないで演習量を増やすことができるか
英語への苦手意識をなくせるかどうか
このレベルの学生は多くの場合、
残念ながら、英語を苦手科目としています・・
最初の方から何度も伝えていますが、
理系で英語が苦手 = 難関大学への合格は難しい
と言うことになってしまいます。
理系だから英語は使わないは通用しない
早い段階で英語への苦手意識をなくすことができるかが、合格へのポイントになります。
もちろん、英語の勉強は適切な段階で適切な勉強をすることができれば、
努力をすることは大前提ではありますが、、、
確実に偏差値70以上まで伸ばすことはできます。
日本語での思考=論理的思考力を高めることができるか
日本で、日本語を使って生まれ育った環境にある人がほとんどだと思います。
成績を上げるためには、大学受験で成績を上げるためには、
論理的に考えることができるのかどうかというのは重要になってきます。
論理的に考えることができると言うのは、
具体抽象、対比、因果関係といった概念操作を
読みながら、できるかどうかと言うことです。
これまでに勉強ができてない = 論理概念の操作が苦手というのがあります
この辺りの思考の訓練はできるようになるために、ものすごい時間がかかります。
ですが、
ここをできるようにならずに合格レベルの力をつけることは不可能です。
昨今、自習管理型の塾が多くありますが、勉強が苦手な人にはあまりおすすめができません。
日本語の理解力がまだ成長しておらず、参考書だけを読んでも理解がほとんどできないからです。
市販の参考書は一定程度の学力、日本語認識能力を前提としているため、
どれだけ良い参考書を読んだところでほとんど理解することはできないのです。
数学の処理能力を高めるためには
できる子とできない子では計算の仕方、処理の速さが全く異なります。
ただしそれは思考の癖であって、訓練によって変えていくことは可能です。
地道な計算を行っていきましょう。
現在早くできている人も、
小さい頃からの地道な鍛錬でできているので、大変ですが、毎日頑張っていきましょう。
数学など計算能力がものをいう科目では、
地道な計算力強化をしていくのが必要です。
『合格る計算』シリーズや、
中学レベルの計算ドリルをまずは高速にできるようにするのが肝心です。
計算力を強くする 完全ドリル : 先を読む力を磨くためにもおすすめです。
最初の数学勉強方針
先ほども述べたように、まずは計算レベルをできるようにしていくのが最優先でしょう。
合格る計算を何度も行っていくことと、
坂田先生の数学シリーズで基本問題の理解を行っていくようにしましょう。
坂田シリーズを活用する
数学ができない子は、残念ながら市販の参考書の答えを見ても理解をすることはできません。
できない原因としては、
それまでの分野の前提知識が抜けているため
式変形が途中でわからなくなるのです。
そこでおすすめなのが坂田先生のシリーズです。
これまでに指導をしてきた生徒で、
数学が苦手な人でもこのシリーズを理解できなかった人はいません。
順番としては、
『坂田アキラの 医療看護系入試数学I・Aが面白いほどわかる本』
で、
簡単に数学1Aの概略を掴んで、
三角関数→指数対数→ベクトル→数学3微分積分で最短で数学3に入ることができます。
それぞれ3回ずつ読んで(解かないで良い)、
理系数学では何をやっていくのかを理解できるようにしていきましょう。
並行して、合格る計算の例題を解いて、
徐々にいろいろな問題を解くように行っていくようにしましょう。
とりあえずこのレベルまで来ると、
普通の参考書を見ても何が書いてあるのかわからない・・というのはないです。
かなり大変ですが、最初の1、2ヶ月でこのレベルまで行ってみると、
飛躍的に数学ができるようになります。
最初の英語の勉強方針
とにかく、英単語を覚えていきましょう。
このレベルの人は圧倒的に英単語が足りません。
できれば中学レベルの英単語から1冊、
並行して高校レベルの英単語帳を1冊覚えるようにしましょう。
英単語を覚えることがとにかく最優先です。
ゴールデンウィークまでにどれくらい覚えることができるかが勝負になります。
自身の知識への紐付けや場所法、イメージ化を使うと覚えやすくなるので、
なんとかして覚えられるようにしましょう。
何度も言いますが、語彙力 = 英語力です。
頑張って覚えましょう。
5,6月までのスケジュール

このレベルからはじめて記述模試で成績を出すのは少し難しいです。
というか、目の前の模試で成績を出すよりも夏・秋口までにどこまでできるようにしていくのかを考えた方が良いでしょう。
英語については、まだ成果が出やすいので、紹介していきます。
まずは英検2級と共通テスト模試で偏差値50程度の成績を出していけるようにしてください。
スケジュールとしては、とにかく単語を覚えるのと、
英文法の基礎、長文内でSVOCをとれるようにしていきましょう
このレベルの受験生は、
英語がどのようなものかがわかっていませんので、
基礎的な中学レベルの英語を読みながら、
SVOCをできるようにしたり、英文法の基礎を身につけるようにしてください。
必要な参考書は?
先ほど述べたようにどの科目も基礎的な参考書を使うようにしてください。
■数学
■英語
8月までのスケジュール

このレベルまで来たら実施すること自体は、かわりません。
英語、数学が55程度までに伸びているかどうかは、かなり重要です。
秋口以降に理科に勉強の比重をシフトしていく必要があるので、
ここで英語、数学でつまづいていた場合はかなり合格が難しくなるので気をつけましょう。
記述偏差値
英語 55
数学 55
理科 50
必要な参考書は?
■英語
■数学
■理科
11月までのスケジュール

この段階で重要なのは理科科目です。
いかにして効率的に理科科目のインプットアウトプットをしていくことができるかどうかです。
特に現役生の場合は、範囲が終わってない・・となると、合格は難しいです。
記述偏差値
英語 60以上
数学 60
理科 55
英語数学については過去問を中心にして、勉強を進めてください。
直前期のスケジュール

基礎学力がついてない場合は、
過去問はたくさんしなくても良いです。
ついつい、周りが過去問をしたくなりますが、、
まだ覚えることが終わってないのに、
1日を過去問の復習で終わってしまうようであれば、
まずは覚えることを覚えることに集中しましょう。
偏差値30程度から合格するためには、他の人と同じことをしているのでは合格することは難しいです。
皆がやっていることを当たり前のように同じことをしていては合格することはできません。
もちろん、単に変なことをしているのではいけませんが、、、
早慶は、普通に勉強をしていても落ちる大学です。
いかに自分なりに工夫をして変わった勉強をすることができるのかが重要なのです。
理科科目をできるようになるためには
今回のブログ記事では、理科については細かくは扱っていません。
具体的な勉強法についてはこちらの記事を参考にしてください。
合格の秘訣とは?
最後にまとめとして、合格の秘訣をお伝えします。
絶対に合格するためには、
情報に左右されずに自身のやるべきことを信じてやり切る
このご時世大量の情報が溢れていて、
それは大学受験の業界でも同じです。
色々な人が色々なことを言っていて、
それに感化されて、
気づいたら勉強をしている自分自身も
できた気になって評論家になってしまいます。
勉強しないで情報ばかり集めて、
「あの参考書がいい」「あの先生の授業がいい」などと色々みて回って、結局何も身につけることができない状態です。
この状態になってしまうと、勉強をしないで、色々なものを評価して満足するので、成績を上げることはできません。
もちろん、このご時世ある程度情報を集めることは重要です。
ですが、過度な情報を集めても、学力は変わらないですし、
勉強が急にできるようになることはありません。
どんな技、テクニック、考え方であっても
継続が肝心です。
何度も何度も繰り返し、
その時に自分なりの気づきを得て、
自分なりの技を磨けるようにしていきましょう。
受かる人はどの参考書を使っても合格ができる!

最後にここまでいってきて元も子もないことを言いますと、、、
受かる子は使うタイミングを間違えなければ、
どの参考書を使っても実力をつけることができて合格までいくことができます。
それはなぜかと言うと、、
先ほどお伝えした継続した努力ができているからです。
ですので、目先の情報に惑わされずにこれを使う!と決めたら、
そこから学ぶことはなくなった・・と言えるくらいまで最後までやり切ることが肝心です。
成績の上がらない子の多くはそれができていません。
本ブログを見た方だけでも、最後までやりきれることをお祈りしています。
頑張ってください!

















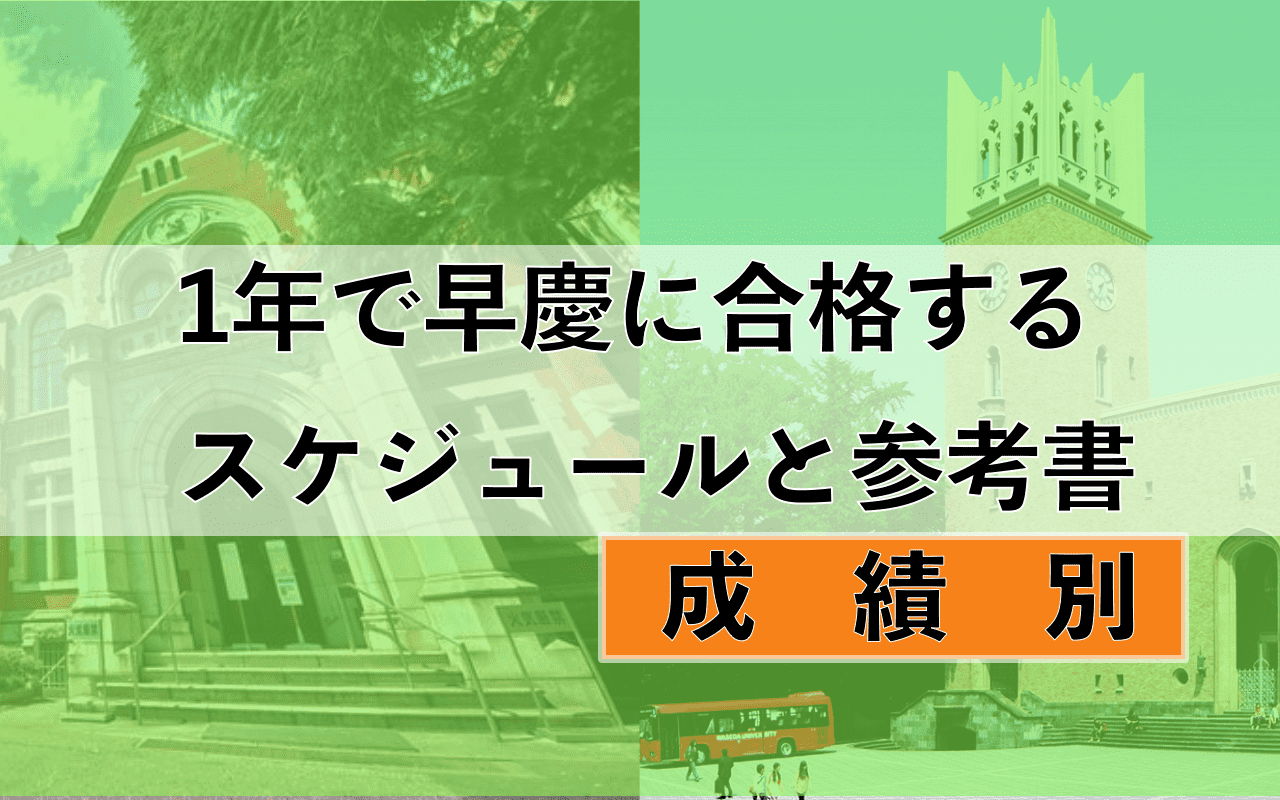











































Published by