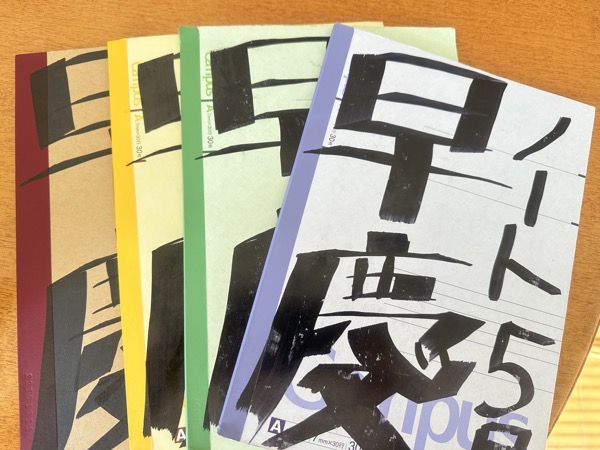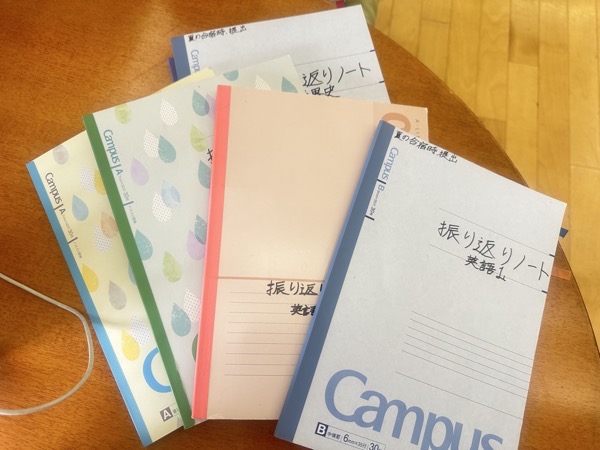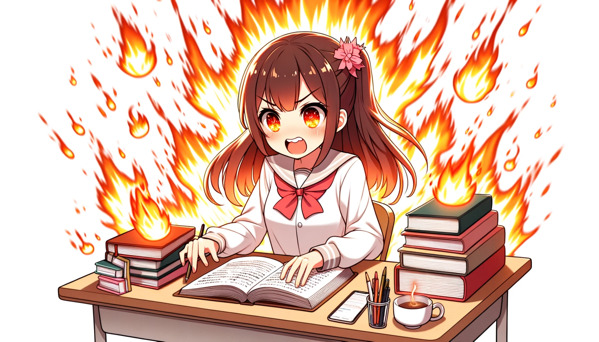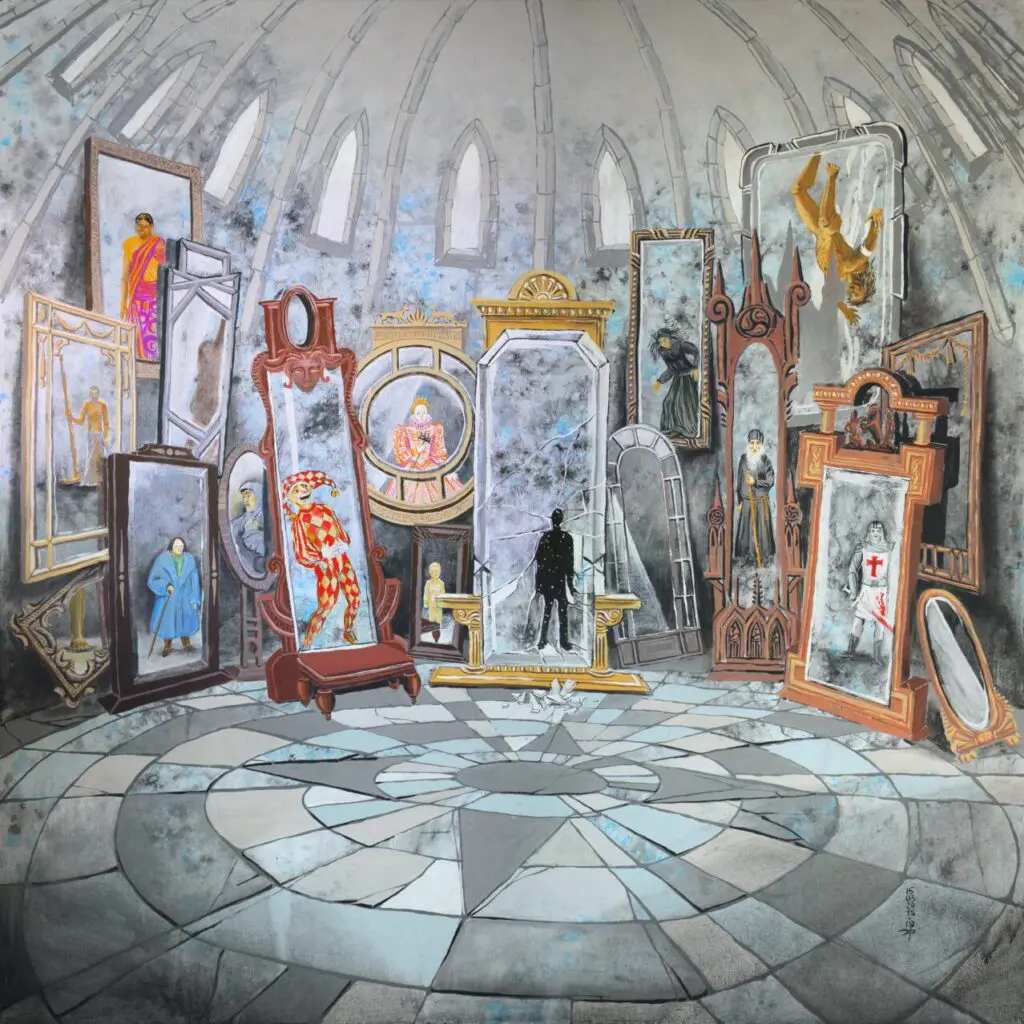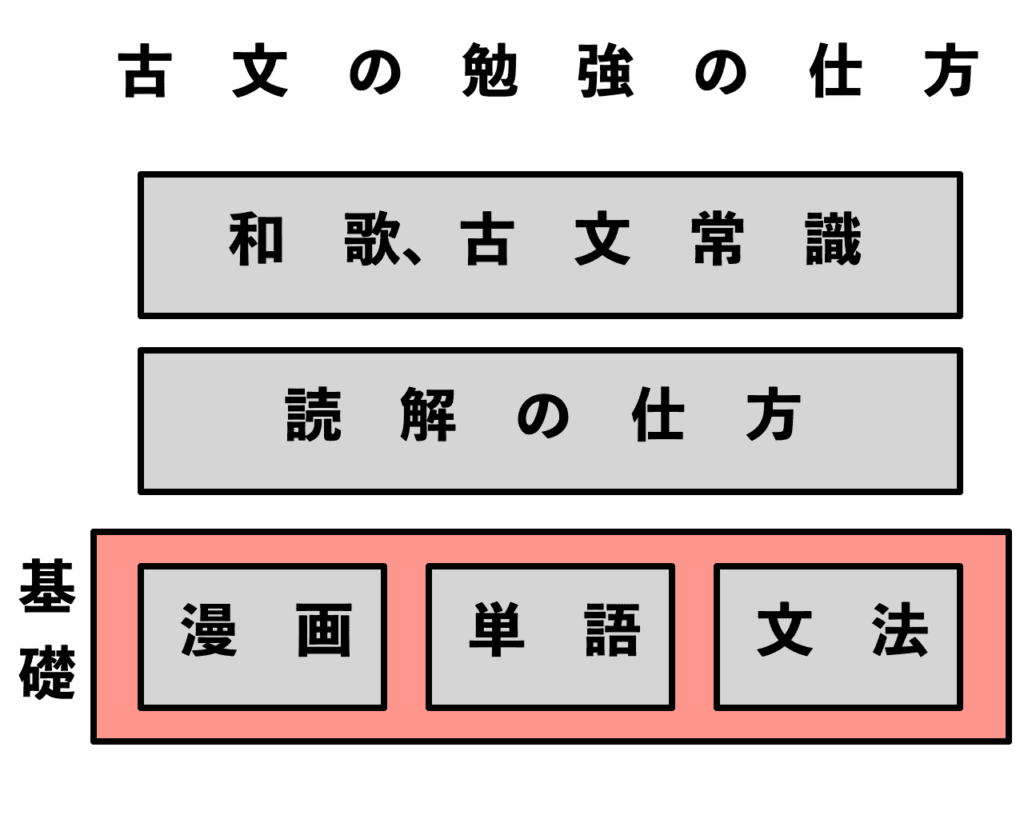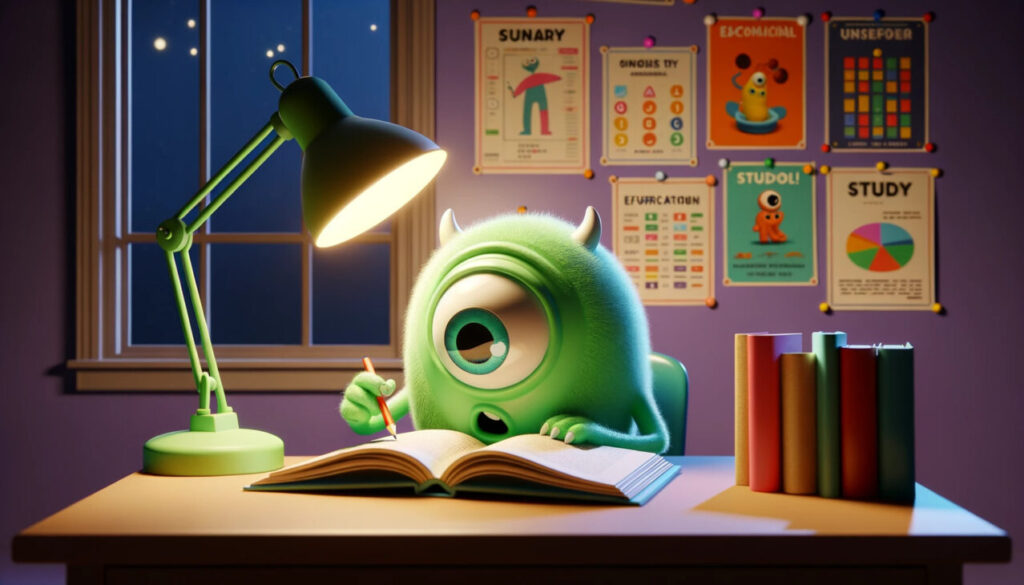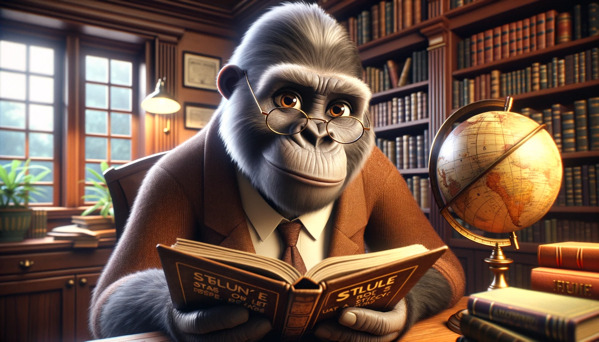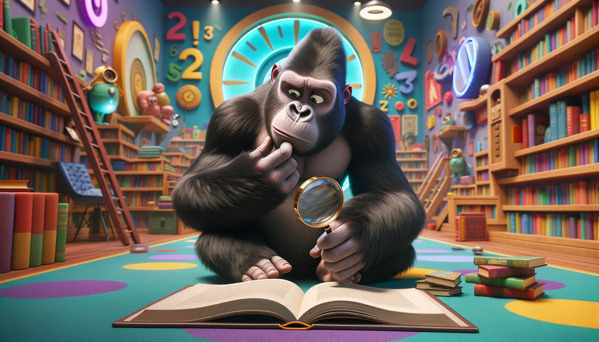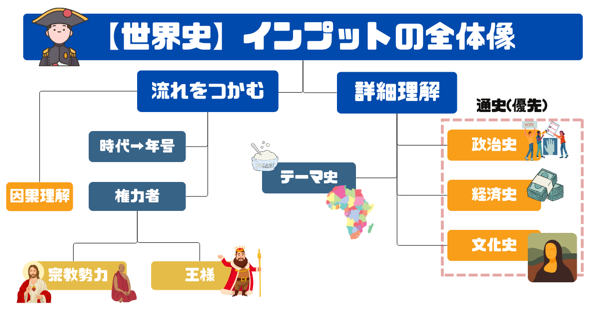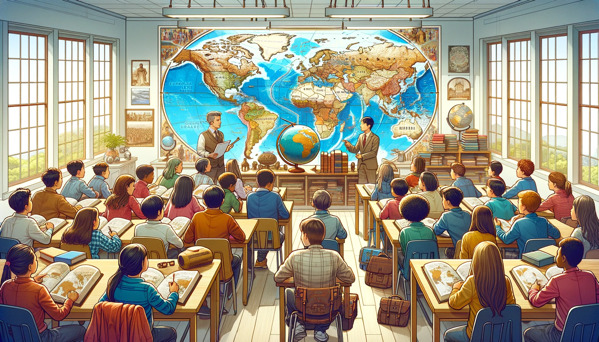中学時代に学習した英語の基礎は、その後の英語学習において非常に重要な役割を果たします。 中学で身につけた英文法や語彙、読解力は、高校や大学での上級英語学習の土台となるからです。 しかしながら、入試英語に慣れていない段階では、中学で学んだ基礎的な英語力不足によりつまずきがちです。 そこで、中学英語の徹
- …続きを読む
- 中学時代に学習した英語の基礎は、その後の英語学習において非常に重要な役割を果たします。
中学で身につけた英文法や語彙、読解力は、高校や大学での上級英語学習の土台となるからです。しかしながら、入試英語に慣れていない段階では、中学で学んだ基礎的な英語力不足によりつまずきがちです。
そこで、中学英語の徹底的な復習と基礎固めが欠かせません。本記事では、英文読解力向上に結びつく中学英語の効果的な学習方法を具体的に解説します。
[toc]
中学時代の英語力が高得点を収める近道であることを踏まえ、
基礎からしっかり起ち上げるためのアドバイスを参考に、中学英語をマスターしていきましょう。中学英語の徹底的な復習が鍵

中学英語の基礎は、英語学習の土台となる大切な要素です。中学で学ぶ英単語や文法は、高校以降の英語学習の土台となる大切な内容です。
しかし、入試英語に慣れていない段階では、中学レベルの英単語や文法でつまずいてしまうことが少なくありません。
例えば、be動詞の過去形や過去分詞、不規則変化の動詞、5文型などの
基本的な文法事項を理解していないと、その後の英文読解は難しく感じられます。また、中学レベルの基本的な英単語がイマイチ定着していないと、英文を読んでいて意味が掴めない場面に遭遇することになります。
そのため、英文読解力を着実に伸ばしていくには、
中学で学んだ英単語や文法を徹底的に復習し、英語の基礎力を固めることが欠かせません。このような基礎が固まっていれば、その後の英文読解の勉強もよりスムーズに進めることが可能です。
英語学習の基礎からしっかり起ち上げることが、英文読解力を高める近道なのです。「英語が苦手・・・」と感じたのであれば、早い段階から中学英語の復習に取り組むことをおすすめします。
中学レベルができれば偏差値60

大学受験の英語で高得点を取るには、中学レベルの基礎がしっかり身に付いていることが不可欠です。
中学で習う内容は単語・熟語、文法、読解力の基礎となるものばかり。
これらをちゃんとマスターすれば、入試範囲の上級レベルの英語もスムーズに習得できます。
具体的には、中学レベルの基本動詞の活用、be動詞、助動詞、動名詞、比較級、関係代名詞などの文法を完全に理解しておくことが必要不可欠です。また、頻出する中学レベルの基本単語や熟語をしっかり記憶することも大切です。
これらの単語・熟語は日常的に使われるものが中心なので、堅苦しい難語ではありません。
ゆっくりコツコツと暗記していけば覚えられます。そして、中学レベルの短文を正確に読解できる力もつけておきましょう。
英文を正しく読み取る訓練は上級レベルに進むための良い下地となります。このように、中学の英語を確実にマスターすれば、高校レベルの英語へステップアップする準備が整います。
その上で、演習を重ねれば偏差値60近くまでは到達できるはずです。
中学で学ぶ英単語や文法をしっかり復習し、英語の基礎力を高めましょう。中学英単語を完璧にマスターする
大学入試の英語を高得点で突破するには、中学レベルの英語力が欠かせません。
中学レベルの基本的な英単語をしっかりマスターしておくことが大切です。中学の英単語は、数こそ多くはありませんが、そのほとんどが日常的に頻出する基本単語です。
これらの単語を完璧に使いこなせるようになることが、英文読解の基礎となります。
例えば、中学レベルの英単語には、time, day, year, people, make, give, takeなどの身近な単語が多数含まれています。これらの単語の意味が分からないと、英文の意味はほとんどわかりません・・・

中学レベルのおすすめの英単語帳
中学レベルの単語帳もいろいろありますが、おすすめは、システム英単語Basic、短文で覚える中学英単語1900です。
苦手な人は中学英単語1900から行ってください。システム英単語 Basic
単語の選定: システム英単語Basicは、
[itemlink post_id="21640"]
高校英語の基礎レベルから標準的な大学入試レベルの単語を網羅しています。
まずは、自分がまだ覚えていない単語を洗い出しましょう。
10単語1セットで学習: 知らない単語を10単語ずつ1セットに分けて勉強しましょう。
これにより、集中力を維持しながら効率的に学習できます。
ミニマルフレーズの活用: システム英単語Basicでは、単語を含むシンプルな例文「ミニマルフレーズ」が紹介されています。
これらのフレーズを使って、単語の意味や使い方を理解しましょう。
繰り返し学習: 単語を定着させるためには、繰り返し学習が重要です。同じ単語に何度も触れることで、記憶に定着させましょう。短文で覚える中学英単語1900
『短文で覚える英単語1900』は、中学英語の基礎固めに最適な参考書です。こ
[itemlink post_id="21638"]
の参考書の特徴は、1つの例文で平均5つの英単語・熟語を、使い方まで含めて学習できる点です。また、文法項目別に4段階のレベル構成があり、
中学での学習順に各文法項目別の例文を易から難の流れに沿って配列しています。この参考書の効果的な使い方は以下の通りです。
- 英単語の本を開きます。
- 1ページ目から始めて、各ページの上にある英語の例文と、その下にある英単語と日本語の意味を見ます。
- その英単語を見て意味が分かるか、例文を日本語に訳せるかをチェックします。
- 知らない単語が合計で30個以下なら、その単語だけしっかり復習します。
- 30から100個くらいの場合は、その単語が使われている例文だけをもう一回読みます。
- 100個以上知らない単語があったら、全ページをもう一回始めから読みます。
2回目以降
- 1回目で30個以上知らなかった単語がある人は、2回目に進みます。
- 例文とその中の単語の日本語訳を確認します。
- 例文を意味を理解しながら読みます。
- 例文を読んだ後、本を閉じて、その例文を覚えているか確認します。覚えていたら、次の例文に進みます。
- 発音が分からない単語は、CDやスマホの辞書で確認します。
このステップを8回くらい繰り返すと、単語や例文が頭にしっかり入ってくるでしょう。
文法からしっかり基礎固めを

英文を正確に読み取る力を養うには、文法力が欠かせません。
中学で学ぶ文法項目は英文読解の基礎となる大切な要素です。中学の文法項目には、be動詞の過去形、過去分詞、助動詞の用法、動詞の時制と法、名詞と代名詞、冠詞、形容詞と副詞、比較級と最上級、5文型などがあります。
これらの文法事項をしっかり理解していないと、英文の構造を正しく読み取ることが困難になります。
例えば、動詞の過去形を理解していないと、英文中の動作の時制が分からず、文章の意味が掴みにくくなってしまいます。そのため、文法の基礎は参考書や問題集を使って繰り返し勉強し、完全に体に染み込ませる必要があります。
文法事項を机上の知識としてではなく、英文を読むための実践的なスキルとして身につけることが大切です。文法の基礎が固まれば、複雑な構文の英文でも混乱することなく正確に意味を読み取る力が身についていきます。
よくある中学英文法の苦手な部分とは?
それぞれの文法項目でどのようなことが苦手なのかを理解して、
自分が理解ができているかどうかを確認してください。- 名詞:可算名詞と不可算名詞の違いがイマイチ分からない。
- 形容詞:形容詞の位置や語順が分からない。
- 動詞:不規則動詞の変化が覚えられない。
- 受動態(受け身):能動態と受動態の違いが分からない。
- 能動態:受動態と能動態の使い分けが難しい。
- 助動詞:各助動詞のニュアンスの違いが分からない。
- 副詞:副詞の位置づけが分からない。
- 前置詞:動詞や名詞との相性が分からない。
- 接続詞:文と文のつなぎ方が分からない。
- 不定詞:不定詞の使い方自体が分からない。
- 人称代名詞:主語との一致が分からない。
- 関係代名詞:whoとwhichの違いが分からない。
- 比較級:比較級の作り方が分からない。
- 最上級:最上級の作り方自体難しい。
- 冠詞:冠詞の必要性が分からない。
- 完了形:完了形の使い方が分からない。
- 仮定法:if以外の接続詞の使い方が分からない。
- 文型:文型の種類自体分からない。
- 時制:過去形と完了形の違いが分からない。
中学レベルだけでもこんなに実施事項があるんですね〜

分詞、関係代名詞はみんな苦手
ここからはみんなが苦手な分詞や関係代名詞を深掘りをしてどのような点が苦手なのかを確認してみます。
分詞がなぜ難しいのか?
分詞は、英文法の中でも理解が難しいトピックの1つです。
なぜ分詞が難しいのか、以下の3点から説明します。形がわかりづらい
分詞には現在分詞(doing)と過去分詞(done)がありますが、ともに動詞の語尾に-ingや-edを加えた形になります。
このため、現在分詞と過去分詞の形の違いが分かりづらく、使い分けが難しいです。
まず形ですが、現在分詞は動詞の末尾に”-ing”を付けるだけです。
例えば、「話す」はspeakなので、現在分詞はspeakingになります。一方、過去分詞は動詞の末尾に”-ed”を付けるのが基本ルールです。
しかし、不規則動詞の場合は”-en”や変化しないものもあるため、形が一定しません。例えば、「話す」はspeakなので、過去分詞はspokenになります。つまり、現在分詞は一定のルールで形を作れますが、過去分詞は動詞によって形が変わるため、現在分詞と過去分詞の形の違いが分かりづらいのです。
意味のニュアンスが似ている
次に意味ですが、現在分詞は「~している」という進行形の意味を表します。
過去分詞は「~された」という受動の意味を表します。
例えば、「割れた窓」は「割られた窓」という受動の意味ですが、
「割れている窓」は「今、割れている窓」という進行形の意味になります。つまり、現在分詞と過去分詞は”日本語で考えてしまうと”意味のニュアンスが非常に近いため、
初学者には使い分けが難しいのです。文法上の位置付けが曖昧
分詞は動詞的な性質と形容詞的な性質を併せ持っています。
文章の中で分詞が使われたとき、それが動詞なのか形容詞なのか判断しづらい場合があります。このように、形が似通っている、意味のニュアンスが似通っている、
文法上の性質が曖昧なため、分詞の使い分けは難易度が高いのです。
ただ、繰り返し例文を通して学習すれば、確実に理解が深まっていきます。
ゆっくりと丁寧に学んでいきましょう。関係代名詞がなぜ難しいのか?
苦手な人が続出する、多くの人が離脱するのが関係代名詞です。

慣れるまでは全然理解できなかった・・・
用法が似ている
関係代名詞にはwho, which, thatなどがありますが、
それぞれの使い方の違いが分かりづらいです。例えば、whichとthatは多くの場合互換可能で、使い分けが難しいです。
まず、whichとthatの使い分けですが、これは非常に紛らわしい点です。
whichは物を指すのに対し、thatは物でも人でも指せます。
しかし、thatのほうが多目的に使えるため、日常会話ではthatのほうが頻出します。
例えば、「I like the car which/that is red」のように、whichとthatはほぼ置き換え可能です。
なんでもthatで大丈夫!とやってしまうと、後々thatの識別の際に理解がし難いので、関係代名詞は識別はできるようにしておいてくださいね
日本語との違いが大きい
関係代名詞という考え方は、日本語には存在しないので最初のうちは全然理解できません。

最初は全然わからなくても大丈夫!
しかし、英語は関係代名詞で1つの文にまとめなければなりません。
これが英語の基本的な構造なので、最初は違和感があると思います。ただ、繰り返し例文を通して覚えることで、英語の関係代名詞の使い方に慣れていきましょう。
ゆっくり理解を深めていけば、自然と使えるようになります。後ろから名詞を修飾することになれる
日本語にはない後ろから名詞を修飾するという考え方に慣れる必要があります。
文法力強化に欠かせない演習の重要性

英文法の力を付けるには、単に知識を覚えるだけでなく、実際に演習問題を解くことが欠かせません。
特に重要なのが、ドリル形式の演習です。
英文法の形やルールはどうしても暗記事項が多くなりがちです。
そのため、まずはドリル形式で同じ形式の問題を何度も繰り返し解き、文法事項の形式やパターンを体で覚えていくことが大切です。
例えば、動詞の過去形のドリルをする場合、過去形にルールに沿って動詞を書き換える練習を毎日10問ずつこなしていく。その上で、4択問題などを通して、文法事項の理解を深めていきます。
ドリルで形式を体に染み込ませた上で、理解力も高めることがポイントです。文法力は、繰り返し行うドリルと理解の両輪が揃って初めて身に付きます。
ドリルが苦手だと思う人もいるかもしれませんが、英文法を学ぶには欠かせない要素です。
飽きずにコツコツ取り組むことが成績アップにつながります。考えずに形を覚えるくらい繰り返す
よく『英文法は理解をしてから暗記をする』と言われますが、
正直偏差値30から始めていたら最初は、
英文法の用語が多すぎて全部を完璧に理解することはできません。なので、最初の段階ではとにかく形を覚えるくらいに何度も繰り返してください。
同じものを50回くらい書いていくとだんだんと意味がわかってきて説明まで目がいきます。中学レベルの英文法をマスターするためのおすすめの参考書
『くわしい 中学英文法』で理解をして、
[itemlink post_id="23390"] [itemlink post_id="23391"]
『英文法パターンドリル 中学全範囲』でドリル形式で形を覚えられるように繰り返し行ってください。
英語ができるようになるために重要なのは、
理解ももちろん大事ですが、まずは形を覚える繰り返すというのがあります。5文型を使った英文構造の理解を深める
英文を正しく読み取るためには、文の構造を理解することが欠かせません。
その基礎となるのが、5文型です。5文型とは、英文の基本的な構造を分類したもので、
主語+動詞からなるSV文型、主語+動詞+目的語からなるSVO文型などがあります。
これらの5文型は、ほとんどの英文の基礎を成しており、
文型ごとの働きや特徴を理解しておくことで、英文の構造を把握しやすくなります。
例えば、SVO文型は「主語が目的語に動詞する」という文の基本パターンです。この文型を理解していれば、英文中に出てきたSVO構造の文を正確に読み取ることができます。
英文解釈は最重要5文型に沿って英文を読んでいく訓練を重ねることで、次第に文構造の理解が深まり、英文の意味を掴み取る力が身についてきます。
英文読解力を上げるには、まず5文型に基づいた文構造の把握から始めるのがコツです。
5文型の理解を通じて、英文を正確かつ深く読む力が培われていきます。英文読解についてどのように行なったら良いのかについてはこちらの記事で詳しく説明しています。
[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/saisokuenglishreading-svoc-structure/"]特に苦手な人は3文型までを完璧に!
特に英語が苦手な人は、まず5文型のうち比較的簡単なSV文型、SVC文型、SVO文型の3文型に取り組みましょう。
- SV文型:主語+動詞から構成される最もシンプルな文型です。「I walk」や「She eats」などがこれに該当します。
- SVC文型:主語+動詞+補語からなる文型で、「主語は補語である」という文になります。「It is red」や「I am a student」などがSVC文型の例です。
- SVO文型:主語+動詞+目的語から構成され、「主語が目的語に動詞する」という文になります。「I read a book」や「She bought a car」がSVO文型です。
この3つの文型をしっかり理解した上で、SVOO文型やSVOC文型に進むのが無理のない学習方法です。
ゆっくり理解を深めながら、最終的には5文型全体を使いこなせるようになりましょう。
基礎レベルの英語構文を理解するためのおすすめの参考書
中学レベルの単語を覚えるのが最低条件ではありますが、ある程度覚えた上であれば、
『大学入試 肘井学の 読解のための英文法が面白いほどわかる本 必修編』が必須の参考書になるでしょう。
難しい単語を使わないで、英語の構造を理解することができるので何度も何度も行って自分のものにしましょう。簡単な教材だと思って侮ってはいけない。これ一冊の内容が完璧になっていれば、早慶レベルの英文の理解も捗ります。
上記教材の保管教材として、
[itemlink post_id="23137"] [itemlink post_id="23392"] [itemlink post_id="17253"]
『大学入試はじめの英文読解ドリル』『英文法基礎10題ドリル』といったドリル教材を使って形を体で覚えていくようにしてください。英文読解の基礎力を培う

英文読解力をつけるには、単語や文法だけでなく、文章内の文のつながり方を理解する力も必要不可欠です。
そのためには、文構造の読み取りやディスコースマーカーの理解が重要となります。例えば、2つの文が「and」や「but」といった接続詞でつながれている場合、
前の文と後の文の論理関係を意識して読み取る必要があります。「and」は前と後ろの文が両方成立するという「追加」の関係、「but」は前と後ろの文が対照的だという「対比」の関係を表しています。
このように接続詞は前後の文の論理を変化させる役割があるため、
接続詞の意味を正確に理解しながら、文章全体の流れを読み取る訓練が必要です。また、「however」「moreover」「therefore」「consequently」などのディスコースマーカーと呼ばれる接続語は、
文章の論旨展開を明示的に示す指標となります。
これらのディスコースマーカーの使われ方を把握することで、段落間の関係性を理解しやすくなります。このように、文法や語彙の習得に加え、文章内の文の接続関係や論理的展開を読み取る訓練を重ねることで、
英文を正しく深く読む力が身についていきます。これが英文読解力アップの基礎を築く第一歩なのです。基礎レベルの英語長文のおすすめの参考書
長文もいろいろとシリーズがありますが、下記2冊をやっているのが良いでしょう。
『速読英単語中学版』を使って単語の抜け漏れを潰していくために使ってもらっても構いません。
[itemlink post_id="23393"] [itemlink post_id="22343"]
その他は『英語L&R レベル別問題集2 初級編』『英語L&Rレベル別問題集3 標準編』をやってください。中学英語をマスター|マインド、戦略編

中学英文法をマスターするためにどのような心持ちで望めば良いのか、
モチベーションの保ち方、戦略の立て方を詳しくお伝えしていきます。学習の継続が成功の鍵
英語力を高めるには、学習の「継続」が不可欠です。基礎的な知識を身につけるのはもちろん大切ですが、それ以上に必要なのが毎日の学習を長期にわたって続けることです。
例えば、単語力は1日に100語ずつ覚えていけば1ヶ月で3000語覚えられます。しかし、1ヶ月間毎日欠かさず学習し続けることは簡単ではありません。
途中でモチベーションが下がったり多忙になったりすると、つい学習が中断してしまいがちです。そこで大切なのが、どんなに忙しくても毎日5分でも10分でも英語に触れる時間を確保すること。
少しずつでもコツコツ積み重ねることで、英語力は確実に身についていきます。まずは英検準2級、つぎに2級を目指す
英語学習のモチベーションを保つには、段階的な目標を立てるのが有効です。
はじめから高い目標を掲げると挫折しやすくなります。
そこでおすすめなのが、まずは英検準2級合格を最初の目標とすることです。英検準2級は中学レベルの英語力があれば合格できるレベルです。
英検準2級の学習期間は2~3ヶ月程度で十分です。
この短期の目標をクリアすることで自信がつき、次のステップへのモチベーションアップにつながります。その次の目標として、英検2級取得を掲げるのが良いでしょう。
2級は高校卒業レベルの英文法力が求められます。
英検準2級取得後、さらに3~6ヶ月程度学習を重ねれば2級取得可能なレベルに上達できるはずです。段階的な目標設定と達成感の積み重ねが、英語学習継続の動機付けとなります。
小さな目標から始めて、着実にステップアップしていきましょう。復習こそが勉強の最大の効率化
勉強の効率を上げるには、復習が欠かせません。
新しいことを学ぶだけでなく、過去に学習した内容を定期的に復習することが重要なのです。
復習は一見時間の無駄に感じるかもしれません。しかし知識を完全に保持するには復習が不可欠です。人の記憶というのは、学習後時間が経てば自然と薄れていきます。
そのため、一度学んだ内容を忘れないよう、
スケジュールを組んで計画的に復習することが大切です。
特に英語のように暗記も必要な教科では、定期的な復習が欠かせません。また、復習の回数を重ねることで学習内容が確実に定着します。
例えば単語を覚える時、初めて目にする単語を5回復習すれば記憶定着率は90%以上になります。つまり復習は、時間のロスや非効率に感じるかもしれませんが、
むしろ学習効果と定着率を高めるのに最も効率的な手段なのです。計画的に復習しましょう。効率的な学習計画の立て方
中学英語をマスターするためには、効率的な学習計画が必要です。
学習期間は個人差がありますが、目安として3カ月を想定して計画を立てましょう。1ヶ月目文法と基礎単語に集中します。文法は中学レベルの内容を1冊の参考書で学習。
単語は中学レベルの単語帳を選び、毎日20-30語ずつ覚えるペースで学習します。2カ月目応用編の単語と熟語、リーディングに取り組みます。難易度が高い単語帳を選び、語彙力強化を図ります。
また、中学レベルの英文を読解する力を養うため、英文読解の入門書に取り組み始めます。3カ月目習得した力を使って英文読解とリスニングに集中します。
中学レベルの英文を正確に読めるように訓練を重ね、リスニングも普段からこまめに取り組みます。
このように段階的に学習していけば、3カ月で中学範囲の英語力は確実に定着するはずです。ポイント各月の学習目標を明確化し、焦らずコツコツと知識を積み上げることです。計画的な学習で効率よく実力を高めましょう。この後の早慶レベルはどうするか?
中学レベルをクリアしたことで、高校レベルの基盤を作ることはできました。
次の段階としては高校レベルも含めた早慶レベルの英語をクリアしていく必要があります。
どのようにしたら良いのか?についてはこちらのブログで説明しています。
[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/program/english-benkyo/"]