早稲田大学文学部日本史勉強法と対策
早稲田大学文学部の日本史試験は、全時代・全分野から出題される難関試験です。
幅広い知識が求められ、正誤問題の選択肢には細かな用語も含まれます。また、大問1の原始考古学と大問6の美術史が必ず出題されるのが特徴です。
本記事では、早稲田大学文学部日本史試験の傾向と対策について解説します。
特徴的な出題範囲、過去問題から見える傾向、効果的な勉強方法、参考書の選び方などを詳しくご紹介します。
早稲田大学文学部日本史試験に確実に合格するためには、的確な傾向把握と計画的な対策が欠かせません。
本記事が早稲田大学文学部日本史試験に挑む皆さんの強力な武器となれば幸いです。
ページ目次
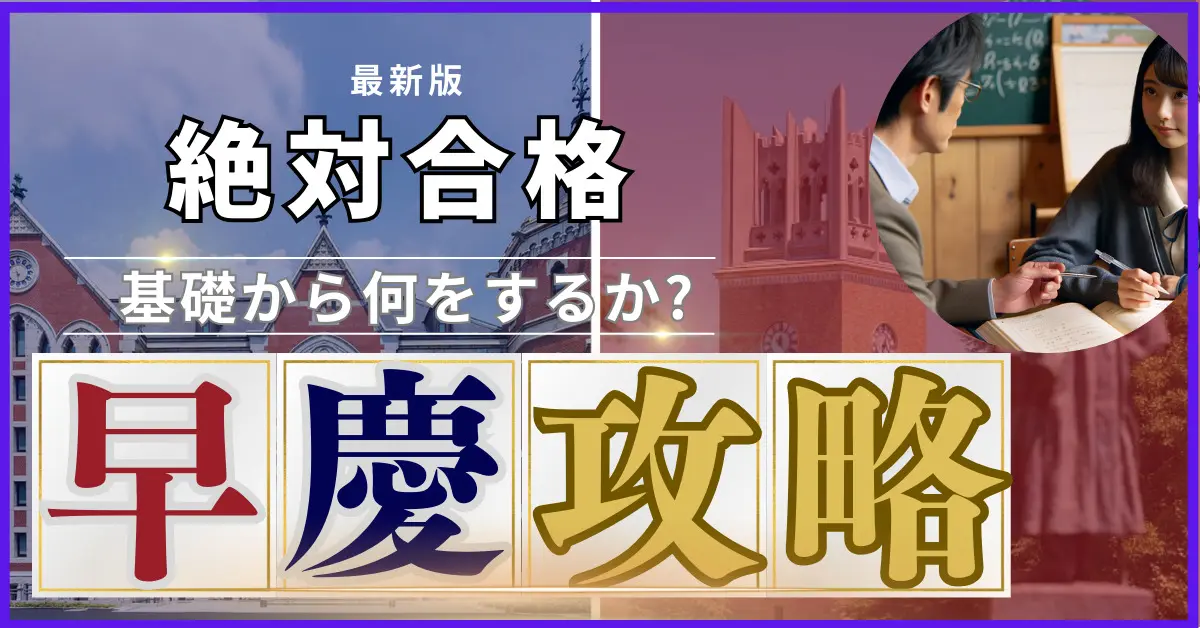
- 【何からはじめたらいい?という人向け】
【まず始めることをお伝えします】 - 早慶に合格するための戦略とは?
1,2年生から合格するための戦略を立てるには? - 【高1】早慶現役合格の勉強法を徹底解説
志望校に合格するためにやるべきこと紹介 - 【高2】現役で早慶GMARCHに合格
必要な勉強法(勉強時間、参考書)を紹介 - 【高2】早慶絶対合格!!のためにすること
勉強時間、スケジュール、参考書、勉強法の紹介
早稲田大学文学部【日本史】の傾向
早稲田大学文学部【日本史】の傾向
早稲田大学文学部の日本史の試験時間は60分で、配点は50点です。
問題形式は、選択問題と記述問題から構成されています。選択問題は正誤判定が主で、記述問題は用語を書く形式です。
出題範囲は原始時代から現代までの全時代で、政治史や文化史など全分野から出題されます。
時代的には、前近代史(古代~江戸時代まで)の出題比重が高く設定されているのが特徴です。
原始時代の考古学に関する問題(大問1)と、美術史に関する問題(大問6)が毎年出題
正誤問題の選択肢には、教科書にはない細かな用語も含まれるので、幅広い知識が必要となります。
早稲田大学文学部【日本史】の特徴
早稲田大学文学部の日本史は、幅広い時代・分野から出題される試験です。
正誤問題の選択肢には細かな用語が出題されることもあり、教科書レベルの知識だけでは足りない場合もあります。
例えば、2018年の入試では「伊治呰麻呂」という人名が正誤問題の選択肢に出題されました。
伊治呰麻呂は8世紀の人物で、光明皇后の詔により遣唐副使として唐に渡来したが、帰国後反乱を起こした人物です。教科書には記載がないため、+αの知識が必要でした。
また、2019年の入試では、正誤問題の選択肢に「山鉾」といった用語が出題されました。
山鉾は神輿の一種で、装飾が施された樅の木を立てたものです。
また、前近代史の出題比重が高く、大問1の原始考古学と大問6の美術史が必出の特徴があります。
大問1では旧石器時代の遺跡である神津島遺跡や細石器の使用に関する知識が問われます。
大問6では絵画や建築物の名称と外観に関する細かい知識が必要となります。
早稲田大学文学部【日本史】への取り組み
- ステップ1: インプット教材の繰り返し学習
- ステップ2: 一問一答で用語を暗記
- ステップ3: 過去問で傾向を掴む
- ステップ4: 大問1、6の特化学習
ステップ1: インプット教材の繰り返し学習
まずは教科書などのインプット教材を繰り返し読み、日本史の基礎知識を固めましょう。原始時代から現代までの通史を抑え、各時代の概要を理解しておきます。
ステップ2: 一問一答で用語を暗記
次に一問一答を解きながら、歴史用語や人名などを暗記していきます。一問一答を繰り返し解くことで、細かい知識も身に付けられます。
ステップ3: 過去問で傾向を掴む
過去問を多く解き、早稲田大学文学部の出題傾向を掴みましょう。正誤問題に慣れ、特徴的な用語も把握します。
ステップ4: 大問1、6の特化学習
大問1の原始考古学と大問6の美術史については、過去問と資料集を使って特化した学習を行います。
こうしたステップを踏むことで、効率的に学習を進められます。基礎から応用まで着実に知識を積み上げていきましょう。
具体的な日本史の勉強法についてはこちらの記事で詳しく説明しています。
早稲田文学部対策:文化史対策

早稲田大学文学部の日本史では、大問6で必ず美術史に関する問題が出題されます。
この文化史の対策はどのようにしたら良いのでしょうか?まずはじめにすることは文化史よりも通史を確実にしておくこと。
文化史=暗記のように感じますが、文化史も通史と同じ流れで進んでいます。この流れを理解できていないと文化史の理解が曖昧になってしまいます。
ですから、まずは通史に重点をおいてみましょう。
その後にようやく文化史です。多くの受験生は文化史=ただの暗記と思ってしまいがちなのですが、文化史にも流れが存在します。
それは人同士の流れと時の流れです。人の流れとは、友人の関係や師弟関係や家族関係などがあたります。
歴史上の人物をただの記号で考えるのではなくて、どのような関係にあったのかを知っておくとわかりやすいですよ。
特に師弟関係は早慶の入試に頻出です。続いて、時の流れです。時の流れというのは、時代ごとの背景ですね。通史と連関してなぜこの文化が発生したのか?という部分を考えてみましょう。
上記のように暗記することでこれまでのような機械的な暗記からさよならすることができます。
過去問を使って考える
1つ例を見てみましょう。
問 空欄( A )について。『闘牛』『敦煌』などの著者としても知られるこの小説家とは誰か。
ア 井上靖 イ 大仏次郎 ウ 司馬遼太郎 エ 菊池寛 オ 吉川英治
細かいと感じるかもしれませんが、受験生の皆さんがよく使っている『石川昌康の日本史B講義の実況中継』のノートに『天平の甍』が記載されています。
鑑真像の材質技法が問1で問われていますが、ちょっとした周辺知識です。努力によってできる問題であるといえます。
その他2018年の入試では、風神雷神図の制作背景に関する知識が問われました。この場合は、風神雷神図のモデルとなった作品や、制作者の俵屋宗達についての知識が必要でした。
2019年の入試では、奈良時代の『過去現在因果経』の図像について問われました。この場合は、同作品が風神雷神をどのように描いているか、作品の内容についての知識が求められました。
他にも、過去には三十三間堂所蔵の風神雷神像や、東照宮の風神雷神像などが題材となっています。
このように、過去問を参考に、特に美術作品の名称、制作背景、内容を中心に学習していくことが重要です。
資料集などを使い、視覚的に作品を確認しながら知識を蓄積していきましょう。
早稲田大学文学部【 日本史で使える参考書
早稲田大学文学部日本史でおすすめの参考書は、「石川実況中継」「東進日本史一問一答」「日本史史料一問一答」「実力をつける日本史100題」「ヒストリア」などです。
「石川の実況中継」で基礎をしっかり身に付け、「日本史一問一答」で細かい知識を蓄えましょう。
その上で、「日本史史料一問一答」で史料対策を行い、「実力をつける日本史100題」「ヒストリア」で総仕上げをするのが良いでしょう。
通史理解とともに、一問一答や過去問で細かい知識と正誤問題対策を積むのが合格への近道です。
早慶レベルの日本史の具体的な参考書はこちらでも記載しています。
早稲田大学文学部に圧倒的な実力で合格できる専門対策

まずは資料請求・お問い合わせ・学習相談から!
早慶専門個別指導塾HIRO ACADEMIAには、早稲田大学専門として文学部への圧倒的な合格ノウハウがございます。
少しでもご興味をお持ちいただいた方は、まずは合格に役立つノウハウや情報を、詰め込んだ資料をご請求ください。
また、早稲田大学文学部に合格するためにどのよう勉強をしたらよいのかを指示する学習カウンセリングも承っています。学習状況を伺った上で、残りの期間でどう受かるかを提案いたしますので、ぜひお気軽にお電話いただければと思います。
⇒ 早稲田大学・文学部に合格したい方は、まずは当塾の資料をご請求ください。







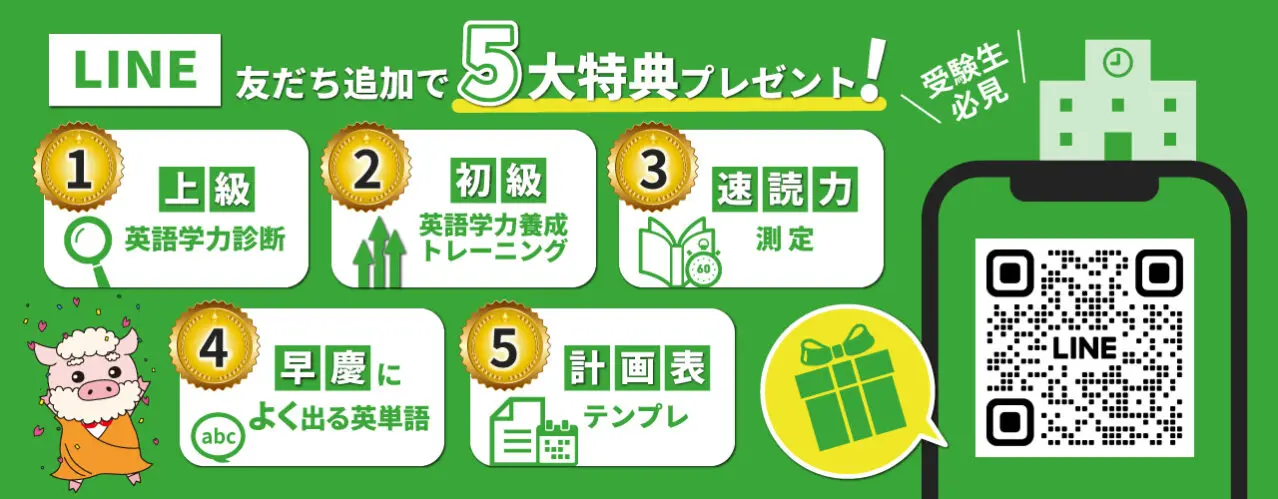





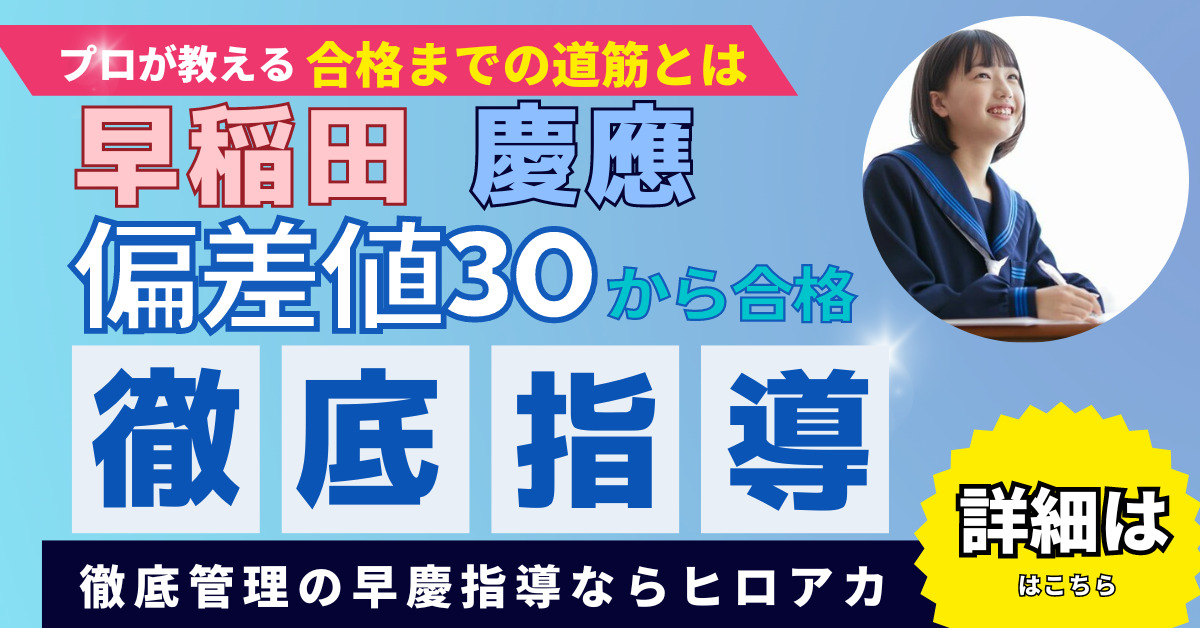

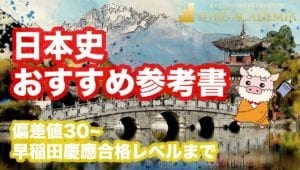
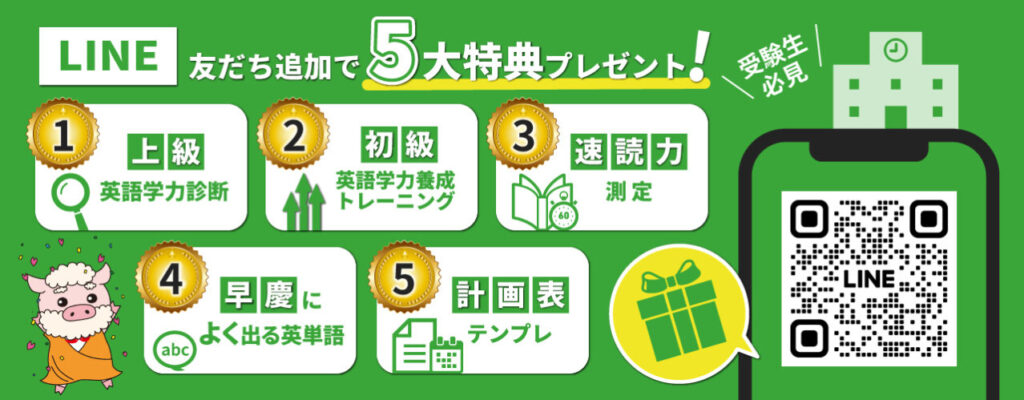
Published by