英文読解の透視図とは?早慶受験に役立つ理由
「早稲田や慶應に合格したいけど、英語の難易度が高くて不安…」「レベルの高い英文読解力を身につけるには、どんな参考書を使えばいいんだろう?」
![]()
そんな悩みを持つあなたへ。「英文読解の透視図」は、早慶合格を目指す受験生にとって、非常に効果的な参考書になりえます。
しかし、その一方で、「本当に早慶レベルで必要?」「難しすぎて使いこなせるか不安…」といった声も聞かれます。
この記事では、「英文読解の透視図」の特徴やレベル感を徹底解説し、早慶受験、特に英語が難しい学部を目指す上で、この参考書が本当に必要なのか、どのように活用すれば効果的なのかを具体的に解説していきます。
具体的にどの学部で必要なのかまで詳しく解説していきます。
ページ目次
英文読解の透視図の特徴とは?早慶受験に役立つ理由
「英文読解の透視図」は、他の参考書とは一線を画す、以下の様な特徴があります。
- 難関大学頻出の高度な文法事項を深掘り
- 実際の入試問題をベースにした実践的な問題
- 詳細な解説で、独学でも理解しやすい
- 別冊付録「英文読解再入門」で基礎力もカバー
特に、仮定法や比較表現、省略、倒置、挿入といった、英文読解の上級レベルに不可欠なテーマを重点的に扱っている点が最大の特徴です。
これらのテーマは、早慶の英語難関学部においても頻出であり、本書をマスターすることで、複雑な構文を正確に読み解く力が身につきます。
別冊英文読解際入門とは?
これは基本的な文法知識を一から確認できる資料で、初学者から上級者まで、自分の理解度に応じて英語の基本を見直すことが可能です。
特に新たな課題に挑む前や、試験前の復習として活用すると、基本的な文法知識をしっかりと身につけることができます。
この付録により、参考書全体としては、初級から上級までの英語学習者が必要とする全ての情報を網羅しています。
とはいえ初学者がいきなり使うには注意が必要ですよ!
![]()
早慶の過去問でこんな英文に苦戦していませんか?
早稲田や慶應といった英語が難しい大学では、以下のような特徴を持つ英文が出題される傾向があります。
- 一文が非常に長い
- 複雑な構文が用いられている
- 抽象的な表現や高度な語彙が使われている
「英文読解の透視図」は、まさにそうした高度な読解力を養うための最適な教材と言えるでしょう。
英文読解の透視図のレベルは?早慶を目指す上での位置付け
「英文読解の透視図」は、標準レベル以上の文法を理解している人を対象としています。
具体的には、以下のようなレベル感が目安となります。
- 共通テストレベルの問題を8割以上安定して解ける
- 河合の模試で英語の偏差値が60程度取れている
- 早慶の英語過去問に少し挑戦してみて、歯が立たないわけではないレベル
本書は、基礎的な文法力を前提に、受験生が間違えやすい点や、難解な文章の解説が中心となっています。
基本的な文法事項に不安がある場合は、「英文読解の透視図」に取り組む前に、基礎を固めることをおすすめします。
皆がやっている難しい教材をやっているから受かるというわけでは決してないので要注意!
早慶合格に向けたレベルアップ
早慶、特に英語難関学部を目指すなら、標準レベルの英文法・解釈問題集をマスターした後に取り組むのが効果的です。
具体的に、基礎から入試レベルまでの精読力をつけるためには英文熟考上・下がおすすめです。
英文熟考の使い方についてはこちらの記事に記載しています。
志望学部によっては透視図を行わなくても、英文熟考だけで十分ですよ
本当の入門レベルは肘井先生の読解のための英文法も良いですよ。
余裕のある人やさらに一段階上の読解力を身につけたい人は、「英文読解の透視図」を使うことで合格に大きく近づきます。

- 【何からはじめたらいい?という人向け】
【まず始めることをお伝えします】 - 早慶に合格するための戦略とは?
合格するための戦略とは? - 【高1】早慶現役合格の勉強法を徹底解説
志望校に合格するためにやるべきこと紹介 - 【高2】現役で早慶GMARCHに合格
必要な勉強法(勉強時間、参考書)を紹介 - 【高2】早慶絶対合格!!のためにすること
勉強時間、スケジュール、参考書、勉強法の紹介 - 早慶満点者インタビュー
早慶圧勝のために具体的に何をしたら良いのか
英文読解の透視図の効果的な使い方(早慶受験生向け)
「英文読解の透視図」を最大限に活用するため、以下の3ステップで学習を進めていきましょう。
ステップ1:基礎固め
- 別冊付録「英文読解再入門」で基本的な文法知識を確認する
- 本書の例文を丁寧に読み込み、構文や文法事項を理解する
- 解説をよく読み、著者の解釈の仕方をつかむ
ステップ2:実践
- 「Challenge問題」に取り組み、実践力を養う
- 解答を参照し、間違えた箇所は解説をよく読んで理解する
- 時間制限を設けて問題を解き、解答スピードを上げる
各章は、文法的に難しいことから和訳に至るまで網羅的な難しい題材を取り扱っているので、英文解釈の力がついていきます。
![]()
ステップ3:復習
- 間違えた問題を繰り返し解き、理解を定着させる
- 解説を読み返し、重要なポイントをノートにまとめる
- 定期的に復習し、記憶の定着を図る
おすすめ使用期間は2か月〜3ヶ月程度です。
早慶の過去問演習と並行して進めるのも効果的です。
問題を解く過程で間違えた場合、その理由を突き止めて同じ間違いを繰り返さないようにするのは重要です。

- 早慶合格のための塾の選び方とは?
学習塾のタイプごとに塾を説明 - オンラインで早慶合格を目指せる塾の比較
1,2年生から合格するための戦略を立てるには? - 集団と個別のメリットデメリット比較
集団、個別に合う合わないは存在します - 【コーチング塾】早慶に合格できない?
コーチング塾の裏事情を暴露 - 【暴露】参考書ルート学習の落とし穴
参考書だけでは合格できないわけとは?
英文読解の透視図を使うメリット
早慶受験において「英文読解の透視図」を使うメリットは以下の通りです。
- 難解な英文を正確に読み解く力が身につく
- 早慶レベルの英語長文読解に必要な知識・スキルが習得できる
- 英語の表現力、特に文章構造の理解が深まる
- 解説が詳細なので、独学でも効率的に学習を進めることができる
英文読解の透視図を使うデメリット
一方で、以下の様な点がデメリットとして挙げられます。
- 初学者には難易度が高すぎて、基礎力がないと使いこなせない
- 解説や例文がやや古く、現代の英語表現とは異なる部分もある
- 受ける学部によっては、本書で扱うには難易度が高すぎる場合もある
基礎をしっかり固めた上で、志望学部に本当に必要かどうかを見極めてから使用しましょう。
英文読解の透視図の文章は古すぎる?
確かに、『英文読解の透視図』は、その刊行年が1993年とやや古いため、
現代の英語学習者にとっては若干取り組みにくいと感じる点も存在します。
その一つが、使用されている英文や解説のスタイルです。
この参考書は、比較的堅苦しいとされる古典的な英文を使用しているため、非常に難易度が高いです。
また、この参考書では、一部の語彙や表現が現代の英語使用においてはあまり一般的でない可能性もあります。
このため、特に英語の新聞や文学作品など、より正式な文脈で使用される表現に親しんでいないと、理解するのに苦労するかもしれません。
しかし、これらの「欠点」は、逆に新たな視点や学習機会を提供するとも言えます。
例えば、より古典的な表現や厳密な文法構造に触れることで、現代の英語表現がどのように進化したのかを理解することができます。
また、あまり使用されない表現や難解な文を読む経験は、読解力を向上させ、英語の理解を深める大きな助けとなります。
早稲田大学国際教養学部の2023年入試において150年前の 文章が出たこともありますので、早慶以上のレベルの高い大学を目指す場合は慣れておく必要があります。
英文読解の透視図は早慶のどの学部で必要ですか?
早慶を受けたい・・から難しい問題を解くという必要はありません。下記に透視図が必要な学部を列挙しておきました。
| 早稲田大学 | 透視図が必要かどうか |
|---|---|
| 政治経済学部 | × |
| 法学部 | △ |
| 文化構想学部 | × |
| 文学部 | × |
| 教育学部 | × |
| 商学部 | △ |
| 基幹理工学部 | △ |
| 創造理工学部 | △ |
| 先進理工学部 | △ |
| 社会科学部 | △ |
| 人間科学部 | × |
| スポーツ科学部 | × |
| 国際教養学部 | ○ |
| 慶應義塾大学 | 透視図が必要かどうか |
|---|---|
| 文学部 | ○ |
| 経済学部 | × |
| 法学部 | × |
| 商学部 | × |
| 医学部 | △ |
| 理工学部 | × |
| 総合政策学部 | ○ |
| 環境情報学部 | ○ |
| 看護医療学部 | × |
| 薬学部 | △ |
透視図をやった方が良い早慶の学部
早稲田大学だと国際教養学部、慶應義塾大学だと文学部、総合政策学部、環境情報学部になります。
透視図をやっても良い早慶の学部
早稲田大学
- 法学部
- 商学部
- 教育学部
- 創造・基幹・先進理工学部
- 社会科学部
慶應義塾大学
- 医学部
- 薬学部
理系は他の科目との兼ね合いを考えて余裕があればやってください。早稲田商学部、社学は解釈よりも単語を覚える必要があるでしょう。
![]()
透視図以外は何がおすすめ?
上級レベルの英文解釈教材として名高い本書ですが、このレベルの教材については透視図とよく比べられるポレポレでも構いません。
この二つの違いについてはこちらの記事で詳しく記載しています。
時間に余裕がある人は「英文解体新書」、「英文解釈教室」をやるのをおすすめします。
英語で成績が出なくてお悩みのそこのあなた!
当塾では、偏差値30からの早慶専門塾として、勉強してどうして成績が出ないのか?を完全に理解しています。英語には勉強のコツがあります。どのようにして英語の成果を上げるのか?対策の一部をこちらのページでご紹介しています。
また、最速で英語の成績を上げたい方は、当塾までご連絡ください。こちらから資料請求をお願いします。



















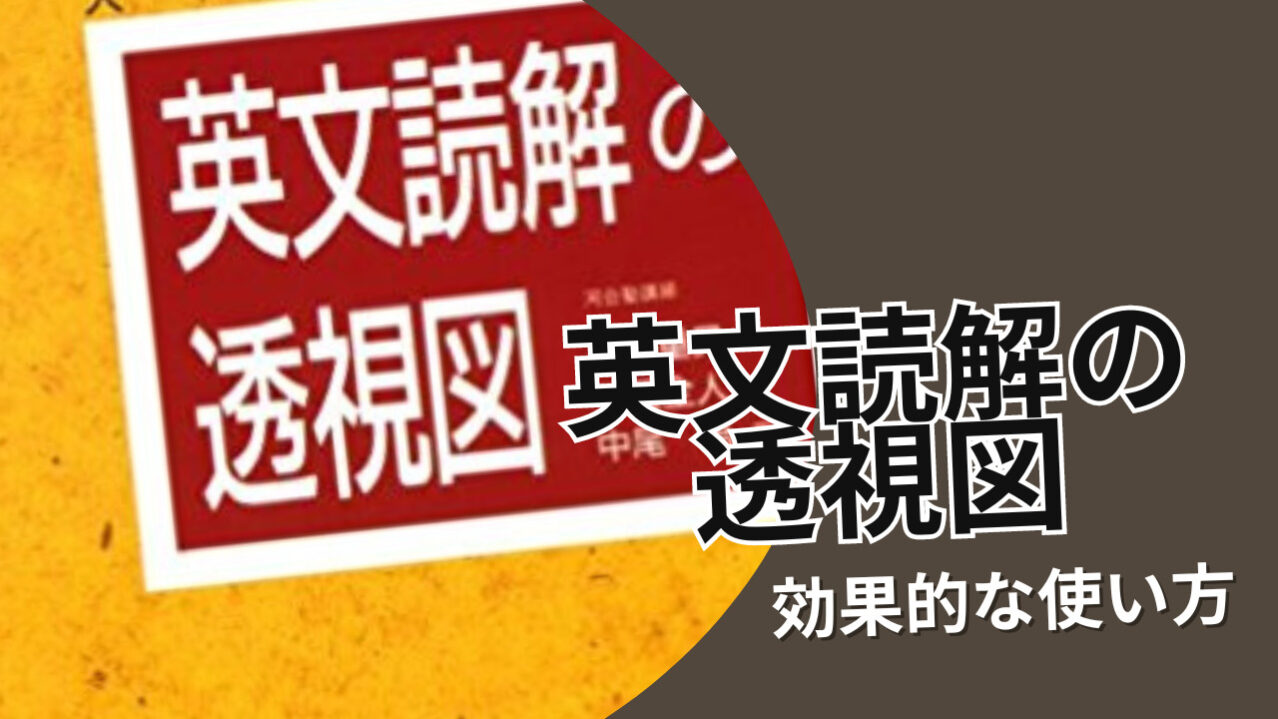





Published by