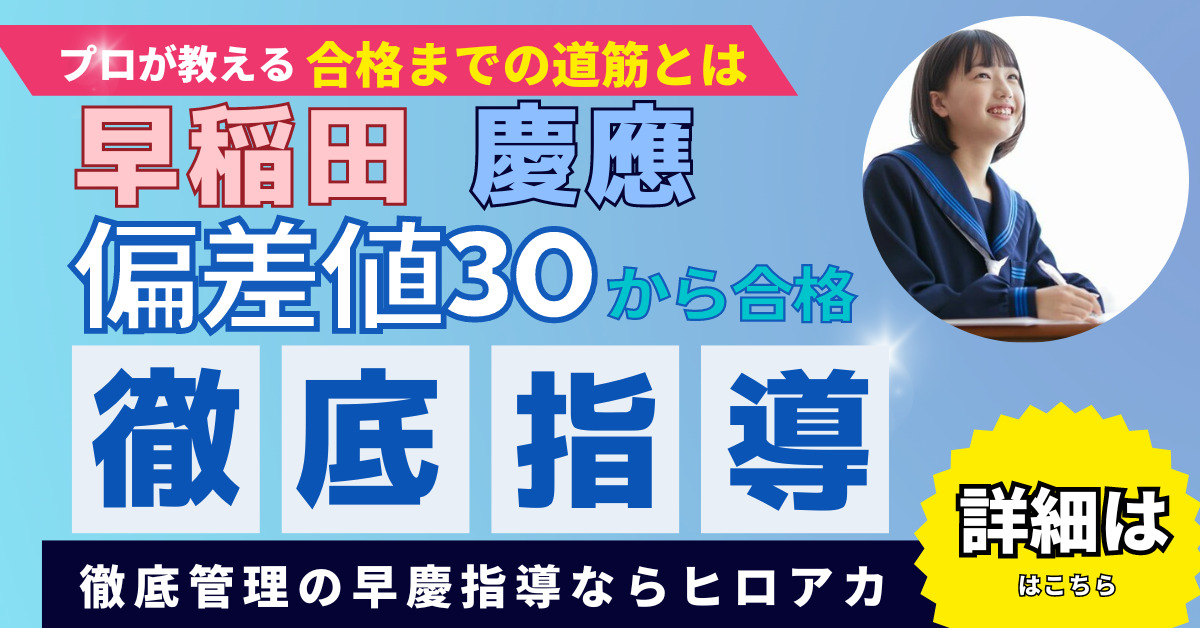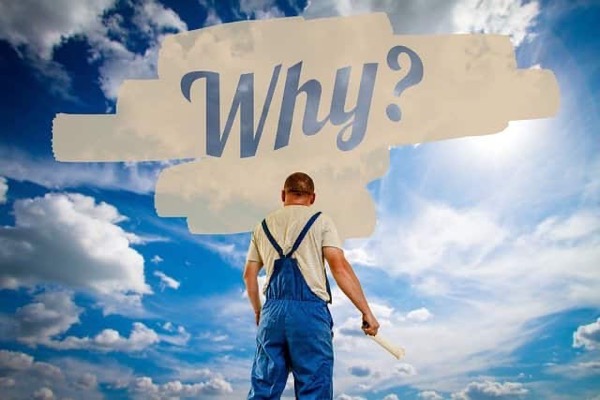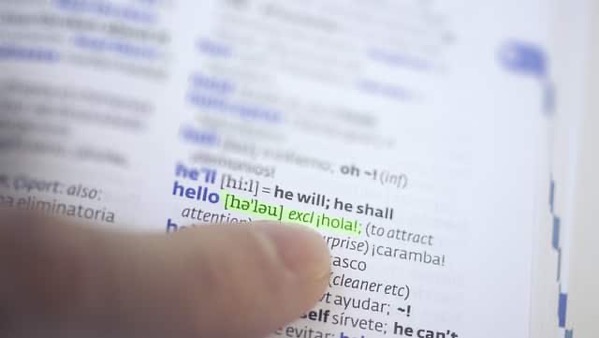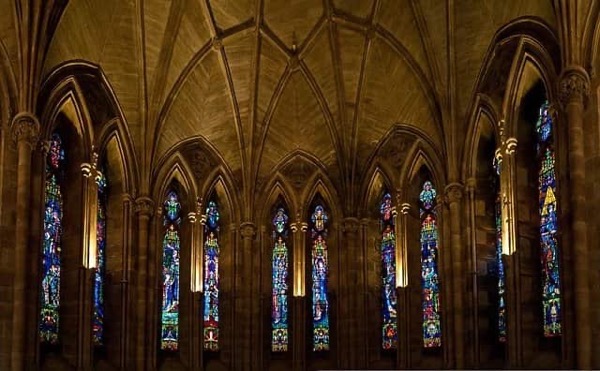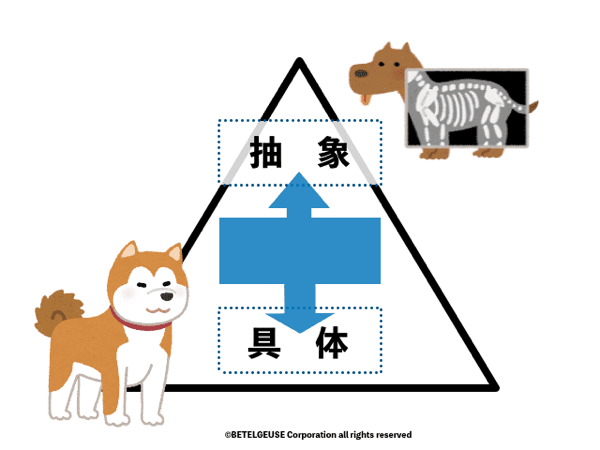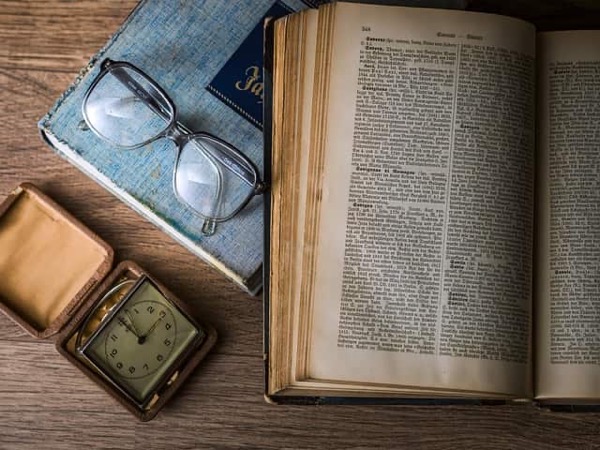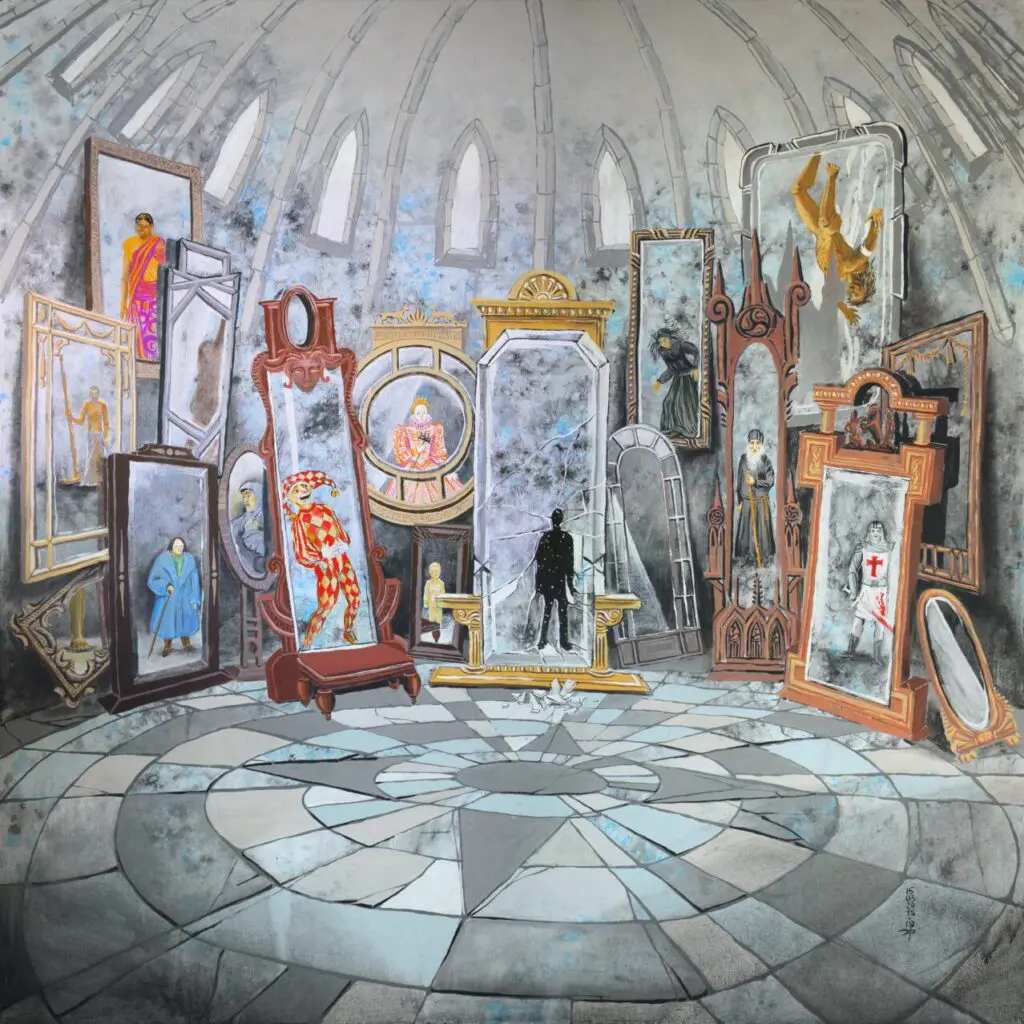こんにちは。早慶専門塾ヒロアカの小野です。
早稲田大学の受験を考えるときに多くの受験生が気になるのが、「どの学部が比較的入りやすいのか?」という点です。
結論から言うと 、早稲田の穴場学部ランキングベスト3は、以下のようになります。
早稲田で合格しやすい学部Top3
1位:国際教養学部
2位:法学部
3位:スポーツ科学部
倍率→倍率スコア
問題の取り組みやすさ→難度スコア
同じ日の日程の大学のレベル→競合スコア
本記事では、これらの基準を踏まえつつ、各学部がなぜ「穴場」と言えるのかを していきます。
[toc]
早稲田大学で受かりやすい学部学科一覧
◆早稲田大学で受かりやすい学部学科ランキング
ひ こ ※本記事では、早稲田理工学部は併願可能性が少ないため、一覧の表から外しました。
各指標の具体的な説明と算出方法
本記事のランキングは、以下の3つのスコアを組み合わせた総合指数 で算出しています。
📊 総合指数の計算式
総合指数 = 0.6 × 倍率スコア + 0.2 × 難度スコア + 0.2 × 競合スコア
倍率(統計的な合格しやすさ)を60%、難度(問題の取り組みやすさ)と競合(同日競合による恩恵)を各20%で重み付けしています。
1. 倍率スコア(0-10点)
実質倍率の低さ を数値化したスコアです。倍率が低いほど高得点になります。
計算式: 倍率スコア = 10 × (12 – 実質倍率) ÷ 9
最低倍率(約3倍)を10点、最高倍率(約12倍)を0点として線形変換
2023-2025年度の3年平均値を使用(最新年度を重視)
小数第2位を四捨五入
※出典:早稲田大学「2025年度/2024年度/2023年度 一般選抜 入試結果」
2. 難度スコア(0-10点)
問題の取り組みやすさ を評価したスコアです。問題が易しいほど高得点になります。
評価基準:
標準的な問題の割合(50%)
時間配分の厳しさ(25%)
記述式問題の負担(25%)
過去問分析と大手予備校(河合塾・駿台・代ゼミ)の難易度評価、当塾の指導実績を総合的に評価しています。
※10点=易、0点=難として10段階で評価
3. 競合スコア(0-10点)
同日競合 による受験層の分散度を数値化したスコアです。競合が多いほど高得点になります。
計算方法:
2025年度の各大学入試日程を基に、同日程で併願可能な主要大学(慶應・MARCH等)の数と受験者層の重複度を以下の重みで評価:
慶應義塾大学:重み 1.0
MARCH上位校(明治・青学・立教):重み 0.6
MARCH(中央・法政):重み 0.4
重み付き合計を0-10点に正規化してスコア化しています。
※最大競合(3校以上)を10点、競合なしを0点として評価
※出典:早稲田大学・慶應義塾大学・MARCH各大学「2025年度 入学試験日程」(2024年10月時点)
※試験日程は年度により変更される可能性があります
なぜこの重み付け(倍率60%、難度20%、競合20%)なのか
重み付けの根拠
倍率を60% とする理由は、実質倍率が最も客観的で予測可能性が高い指標だからです。早稲田志望者は基礎学力が高く、問題難易度差より競争倍率の方が合否に直結します。
難度・競合を各20% とする理由は、英作文や時間制約、同日競合の影響は一定あるものの、倍率ほどの決定的要因ではないためです。
重要
この重み付けは「統計的な受かりやすさ」を示すものです。個々の受験生の得意科目によって実際の受かりやすさは大きく変わります。
上記表は学部学科でしたが、説明については学部ごとに説明 をしていきます。
早稲田で受かりやすい1位 国際教養学部(SILS)
国際教養学部(SILS)は総合指数8.56 で早稲田大学内で最も合格しやすい学部 です。英語重視 の入試形態が特徴で、英語力に自信がある受験生には有利な学部と言えます。同日に慶應・MARCH上位校との競合があるため、受験層が競合しやすく、統計上の入りやすさが生まれています。
国際教養学部の倍率
倍率スコア:10.00(実質倍率の平均 約3.0倍) 。近年は実質倍率が低めに安定しており、早稲田大学の中では比較的チャンスのある学部です。英語重視層が慶應・MARCH上位 へ同日併願で流れるため、統計上の「入りやすさ」が生まれています。
最新3年の実質倍率
学科・方式
2025
2024
2023
平均
国際教養学部
3.4
3.2
2.7
3.03
※出典:早稲田大学入学センター「入試結果」より算出。詳細は早稲田大学公式サイト をご確認ください。
国際教養学部の競合
競合スコア:10.00(最大) 。慶應(経)・明治(文)・青学(文/教育)・立教(全学部)・中央(商)などと重なり します。同じ英語得意層が複数大学に競合 しやすく、母集団の競争圧が下がりやすいのが特徴です。この競合効果により、実質的な競争率が緩和される傾向にあります。
※2025年度入試の場合、2月13日に慶應経済A方式、明治文学部、立教全学部日程などと競合。詳細な日程は各大学の入試要項をご確認ください。
国際教養学部の難易度
難度スコア:2.80 。読解自体はこのレベルでは標準帯ですが、Writingは例年「自由英作文×2+日本語要約×1」の3題構成(60分)。時間内に論旨一貫・根拠付きで書き切る運用力が必要となり、英語の総合力が問われます。単なる読解力だけでなく、論理的思考力と表現力が求められる試験です。
入試問題自体は、読解問題は早稲田国教の受験者層を考えると、英語が得意な生徒であれば、十分満点近くの点数が取れるレベルです。
ライティングが他大学を受ける人からすると難しいです。
早稲田国際教養学部の英語対策について、ライティング問題の具体的な解法と時間配分のコツ を詳しく解説しています。特にWriting対策で差をつけたい方は必見です。
[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/kokkyo/wkokkyou-english/"]
国際教養学部のメリット・デメリット
SILSのメリット
倍率が低め で推移:統計上の入りやすさがある競合が最大 :同日競合により受験層が割れ、チャンスが増える英語を武器 にできる受験生ほど、再現性のある得点設計が可能
SILSのデメリット
記述負荷が大 :要約・自由英作の完成度と時間配分で失点が大きくなりやすい表現精度の要求 が高い:論理の一貫性/段落構成/語彙選択が合否に直結細部の方式は年度で微調整あり:最新要項の確認が必須
早稲田で受かりやすい2位 法学部
法学部は総合指数7.34 で早稲田大学内で2番目に合格しやすい学部 です。読解精度×情報処理 を堅実に積み上げるタイプの試験で、設問の安定性が高く、同日競合が多いため競合の恩恵も受けやすいのが特徴です。正確性重視の受験生には向いている学部と言えます。
法学部の倍率
倍率スコア:7.67 。実質倍率は約4.7倍で推移しており、統計的に見て合格しやすい水準です。スポーツ科学部や国際教養学部と比べると倍率面での優位性はやや低いものの、十分に狙い目の学部と言えます。
最新3年の実質倍率
学科・方式
2025
2024
2023
平均
法学部
5.3
4.6
5.3
5.1
法学部の競合
競合スコア:6.21 。慶應・明青中などと幅広く重なる ので、受験層が割れやすい配置です。この競合効果により、実質的な競争が緩和される傾向にあります。
法学部の難易度
難度スコア:7.50 。長文の情報密度と一部記述(要約など)で精度と時間配分 が要求されます。単なる速読力だけでなく、正確に内容を把握し、論理的に記述する力が求められる試験です。
早稲田の中でも最難関学部の一つである法学部です。
ですが、早稲田の中でも倍率は低めです。
合格ができるかどうかは、150字程度の要約に国語に時間を回せるかどうかがポイント になるでしょう。
どの科目も記述問題があるので、記述力がポイント になります。
【早稲田大学法学部|英語】各設問の徹底対策 早稲田大学法学部 国語| 偏差値30から本番で圧勝するための徹底対策 早稲田大学法学部 世界史 | 偏差値30から本番で圧勝するための徹底対策 【早稲田大学法学部|日本史】各設問の徹底対策
法学部のメリット・デメリット
法学部のメリット
形式が安定 しており、根拠に戻る読み とケアレス抑制 で得点が安定競合効果が大 で、同日競合の流出に助けられやすい正確性重視の受験生に再現性が高い
法学部のデメリット
ミスのコストが高い(正誤・空所補充で一問の重み が大きい)
速度×精度 の両立が必要で、緩い読みでは伸びない倍率は中位帯で油断しにくい
総合指数:7.34 (倍率 7.67/難度 7.50/競合 6.21)
早稲田で受かりやすい3位 スポーツ科学部
スポーツ科学部は、総合指数7.14 で早稲田大学の中で3番目に合格しやすい学部 となっています。倍率の低さ と問題の取り組みやすさ が最大の特徴です。共通テスト主体の試験方式で対策を一本化しやすい一方、小論文の有無・配点が合否を左右する点に注意が必要です。
スポーツ科学部の倍率
最新3年の実質倍率
学科・方式
2025
2024
2023
平均
スポーツ科学部
4.6
2.8
2.5
3.30
倍率スコア:8.79 (今回セット中の最上位)。実質倍率が2.7倍と低く、統計上は最も拾いやすい 部類です。この低倍率は、受験生にとって大きなアドバンテージとなります。
スポーツ科学部の競合
競合スコア:0.00 。同日競合がほぼなく、競合の恩恵は期待しにくい 構造です。他大学との日程重複が少ないため、受験層が競合せず、スポーツ科学部を志望する受験生が集中しやすい傾向にあります。
スポーツ科学部の難易度
難度スコア:6.71 。共通テスト主体の試験で、標準的な問題が中心 です。ただし、年度によっては小論文(資料型/PISA型) が課される場合があり、その対策が必要です。基礎から標準レベルの問題をしっかり押さえることで、高得点が狙える学部です。
スポーツ科学部のメリット・デメリット
スポ科のメリット
倍率優位が最大級 で、基礎~標準問題の精度勝負に持ち込みやすい共通テストに一本化した学習設計 が可能(科目展開が読みやすい)
形式のブレが小さく、演習量が得点に直結 しやすい
スポ科のデメリット
小論文の有無・配点で合否が大きく動く (未対策だと上位でも落とす)競合が弱く、当日の自力勝負 になりやすい
共通テストの取りこぼしは挽回が難しい
総合指数:6.62 (倍率 8.79/難度 6.71/競合 0.00)
早稲田で受かりやすい4位 教育学部
教育学部は総合指数6.92 (英語英文学科が学部内最高)で早稲田大学内で4番目に合格しやすい学部 です。学部全体として標準〜やや易 寄りの問題傾向が特徴で、基礎から標準レベルの徹底が合格につながりやすい学部です。学科ごとに特色があり、自分の得意科目を活かした選択が可能です。
教育学部の各指標の具体的な説明
教育学部は方式が近く、学部全体として「標準〜やや易」寄り (ただし英文が長文化傾向)。ここでは学部全体の指標に加え、学科ごとの数値差 を明確に示します(数値は0–10化、総合指数は倍率0.6+難度0.2+競合0.2)。
教育学部の倍率
教育学部は学部学科ごとに倍率が異なります。英語英文学科は比較的倍率が低い傾向にありますが、英語の配点が大きいです。
最新3年の実質倍率
学科・専修
2025
2024
2023
平均
初等教育学専攻
9.5
10.4
14.8
11.57
国語国文学科
6.7
5.8
5.1
5.87
英語英文学科
4.4
3.4
4.6
4.13
社会科(地理歴史専修)
8.2
6.1
8.4
7.57
教育学科(教育学専修)
7.6
7.2
7.3
7.37
教育学科(生涯教育学専修)
14.5
12.6
5.7
10.93
教育学科(教育心理学専修)
8.9
10.1
8.3
9.10
社会科(公共市民学専修)
5.5
4.6
6.0
5.37
複合文化学科
5.9
5.0
5.3
5.40
学科別の倍率スコア(高いほど易)と実質倍率は以下の通りです。
英語英文学科:倍率スコア 8.74 (実質約3.53倍 )
国語国文学科:7.02 (約4.48倍 )
初等教育学専攻:1.87 (実質約10.32倍 )
社会科(地理歴史専修):3.37 (約8.97倍 )
社会科(公共市民学専修):7.68 (約5.37倍 )
教育学科(教育学専修):4.76 (約7.71倍 )
教育学科(生涯教育学専修):3.04 (約9.27倍 )
教育学科(教育心理学専修):3.42 (約8.92倍 )
複合文化学科:7.65 (約5.40倍 )
→ 学部内では英文、国文、初等の順 に倍率面で有利です(倍率スコアが高いほど有利)。
教育学部の競合
競合スコア(学部内ほぼ共通):2.75 。主な同日競合は上智(TEAP2次)・青学(経済) など。SILSほどの大きな競合は起きにくい一方、致命的に不利 な日程でもありません。
教育学部の難易度
教育学部は総じて標準〜やや易 。ただし長文化(特に英語) で時間配分が難所となります。学科別の難度スコア(10=易)は以下です。
初等教育学専攻:7.00 (標準〜やや易。長文読み切りが課題)
国語国文学科:7.00 (標準〜やや易。古文・現代文の安定感が効く)
英語英文学科:5.00 (英文の密度が高く、やや重い)
社会科(地理歴史):5.20 (資料読解を含み中程度の負荷)
教育学科(教育学/生涯/教育心理):各5.20 (標準帯、語数負荷に注意)
→ 難度面では初等・国文がやや有利 。英文は問題密度のぶん、訓練が必要です。
2022年より英語の問題に大きな変更がありました。
次年度以降はまだどうなるか不明ですが、取り組みやすかったそれまでと比べると超長文になりましたので、避ける受験生が増える可能性が大きくあるでしょう。
教育学部英語の長文化について
2022年度以降、早稲田教育学部の英語は大幅に長文化しました。総語数が従来の約1.5倍に増加し、時間配分の難易度が上がっています。
早稲田教育学部の英語対策について、超長文化した読解問題の攻略法と時間配分の戦略 を詳しく解説しています。長文読解で高得点を狙いたい方は必見です。
[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/kyoiku/wkyouiku-english/"]
教育学部のメリット・デメリット
教育学部のメリット
倍率が総じて低〜中 で、統計上の取りやすさがある出題は標準〜やや易 寄り:基礎〜標準の徹底 で合格点に届きやすい
学科ごとの特色で、得意科目を活かした選択 が可能(初等・国文は特に狙い目)
教育学部のデメリット
英語が長文化 しがちで、時間配分を誤ると得点が不安定
競合効果が中程度 のため、SILSほどの”他校流出”恩恵は小さい不得意科目を残すと配点の重さ で失点が大きくなりやすい
学部代表(初等教育学専攻)総合指数:7.78 (倍率 9.71/難度 7.00/競合 2.75)
学部内レンジ(総合指数) :5.94 ~ 7.78
国語国文学科:総合 7.01 / 英語英文学科:6.40 / 社会科:6.29
教育学(教育学):6.11 / 生涯教育:6.09 / 教育心理:5.94
早稲田で受かりやすい5位 人間科学部
人間科学部は総合指数6.92 (健康福祉科学科が学部内最高)で早稲田大学内で5番目に合格しやすい学部 です。資料読解・思考力型 の要素を含みつつ、全体としては標準~やや易の問題傾向が特徴です。慶應SFC等と同日で、競合の恩恵も期待できます。
人間科学部の倍率
学部平均の実質倍率:約5.5倍 (3学科平均)。学科別では健康福祉科学科が5.33倍と最も低く、人間環境科学科が5.70倍とやや高めです。
最新3年の実質倍率
学科・方式
2025
2024
2023
平均
健康福祉科学科
4.9
6.0
4.0
5.33
人間情報科学科
4.4
6.0
4.5
5.50
人間環境科学科
5.7
5.5
5.9
5.70
学部平均(単純) 5.90 5.83 4.80 5.51
健康福祉科学科:倍率スコア 7.44
人間情報科学科:7.33
人間環境科学科:7.04
学部内では健康福祉 > 情報 > 環境 の順で倍率面の有利度が高い(値が高いほど易)。
人間科学部の競合
競合スコア:全学科 5.65 。慶應SFC(総政・環情)や青学(地球社会など)と同日で、競合が効きやすい 構造です。この同日競合により、受験層が他大学に流れやすく、実質的な競争率が緩和される傾向にあります。
人間科学部の難易度
難度スコア:全学科 7.50 (やや易)。資料・統計リテラシーは要るものの、記述負荷は限定的 です。基礎から標準レベルの問題が中心で、論理的思考力と資料読解力があれば高得点が狙えます。
人間科学部のメリット・デメリット
人間科学部のメリット
競合が中~大 で、同日流出の恩恵が見込める難度がやや易 で、基礎+論理整理の徹底が効く資料・統計に強い受験生は差をつけやすい
人間科学部のデメリット
教材が発散しやすく、形式に寄せた演習設計 が必要
年度によっては分量負荷 が増し、時間配分の難易度が上がる
倍率は中位帯で楽観は禁物
学部代表(健康福祉科学科)総合指数:6.31 (倍率 6.13/難度 7.50/競合 5.65)
人間情報科学科:総合 6.16(倍率 5.88/難度 7.50/競合 5.65)
人間環境科学科:総合 5.98(倍率 5.59/難度 7.50/競合 5.65)
早稲田で受かりやすい6位 政治経済学部
注: 政治経済学部は学科により順位が異なります。ここでは学部の代表として政治学科(4位)を基準に説明しますが、国際政治経済学科は5位、経済学科は14位となります。
政治経済学部は総合指数6.43 (政治学科が学部内最高)で早稲田大学内で6番目に合格しやすい学部 です。総合問題(資料・英語・記述) の比重が高く、問題の”重さ”が最大の壁です。倍率は低めに見えても、難度スコアが低い ため、総合指数では中位に留まっています。
政治経済学部の倍率
学部平均の実質倍率:約3.8倍 (3学科平均)。政治学科と国際政治経済学科は3.3~3.4倍と低めですが、経済学科は4.50倍とやや高めです。
最新3年の実質倍率
学科・方式
2025
2024
2023
平均
政治学科
3.4
3.4
3.2
3.33
国際政治経済学科
3.2
2.7
4.3
3.43
経済学科
4.9
4.0
4.6
4.50
学部平均(単純) 3.93 3.37 4.03 3.78
政治学科:倍率スコア 9.63
国際政治経済学科:9.43
経済学科:8.46
倍率面では政・国政経 > 経済 。政治学科と国際政治経済学科は倍率面で有利です。
政治経済学部の競合
競合スコア:全学科 0.61 。主な同日競合が限定的で、競合の恩恵は小さい 配置です。他大学との日程重複が少ないため、受験層の競合効果はあまり期待できません。
政治経済学部の難易度
難度スコア:全学科 2.66 。和文読解+英文読解+自由英作など、記述・統合処理 の負荷が高いのが特徴です。複数の資料を統合して論理的に記述する力が求められ、時間配分の難易度も高い試験です。
早稲田政治経済学部の総合問題対策について、資料読解・英文統合・記述問題の攻略法 を詳しく解説しています。総合問題で高得点を取るための戦略を知りたい方は必見です。
[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/waseda/seikei/seikei-sogo/"]
政治経済学部のメリット・デメリット
政経のメリット
思考力型 の受験生にはフィットしやすく、上振れが出やすい 過去問の傾向が掴めれば、設問別テンプレ で再現性を作れる
倍率面は相対的に有利(特に政・国政経)
政経のデメリット
総合問題の重さ で難度スコアが伸びにくく、時間配分の失敗 が致命傷に競合が小さく、倍率以外の追い風が弱い
対策の着手が遅いと完成度が間に合いにくい
学部代表(政治学科)総合指数:6.37 (倍率 9.52/難度 2.66/競合 0.61)
国際政治経済学科:総合 6.18(倍率 8.93/難度 3.50/競合 0.61)
経済学科:総合 5.17(倍率 7.25/難度 3.50/競合 0.61)
早稲田で受かりやすい7位 文化構想学部
文化構想学部は総合指数5.21 (英語4技能利用が学部内最高)で早稲田大学内で7番目に合格しやすい学部 です。読解+要約 の同型形式が特徴です。競合は中~大ですが、倍率が重くのしかかる 配置で、特に一般方式は倍率面で不利です。
文化構想学部の倍率
学部平均の実質倍率:約8.1倍 (2方式平均)。一般方式は9.1倍と非常に高く、英語4技能利用でも7.1倍と高めです。倍率面では厳しい戦いを強いられる学部です。
最新3年の実質倍率
学科・方式
2025
2024
2023
平均
英語4技能利用
7.0
6.9
7.4
7.10
一般方式
10.0
8.5
8.8
9.10
学部平均(単純) 8.50 7.70 8.10 8.10
英語4技能利用:倍率スコア 4.54
一般方式:3.44
一般方式は倍率スコアが極めて低く、統計的に不利 。英4技能は相対的にマシですが、それでも厳しい戦いです。
文化構想学部の競合
競合スコア:両方式 6.05 。立教・中央法・法政などと重なり、競合の恩恵は中~大 。同日競合により受験層が他大学に流れやすく、実質的な競争率が緩和される効果があります。
文化構想学部の難易度
英語4技能利用:難度スコア 6.41
一般方式:6.68
いずれも標準帯。要約の運用力 で差が出やすく、論理的な文章構成力と時間配分が求められます。
文化構想学部のメリット・デメリット
文化構想のメリット
競合が効く ため、同日併願の設計次第で上振れが出る読解・要約型 に強い受験生は再現性を作りやすい
文化構想のデメリット
一般方式は倍率の不利 が大きい語数と要約で時間が足りなくなる 受験生が多い
学部代表(英語4技能利用)総合指数:5.21 (倍率 4.54/難度 6.41/競合 6.05)
一般方式:総合 4.61(倍率 3.44/難度 6.68/競合 6.05)
早稲田で受かりやすい8位 文学部
文学部は総合指数5.11 (英語4技能利用が学部内最高)で早稲田大学内で8番目に合格しやすい学部 です。文化構想と形式が近似(読解+要約 )で、競合は強めですが、倍率の重さ が大きな課題です。文化構想学部と同様、高倍率との戦いを強いられる学部です。
文学部の倍率
学部平均の実質倍率:約7.5倍 (2方式平均)。両方式とも7倍台で推移しており、倍率面では厳しい状況が続いています。
最新3年の実質倍率
学科・方式
2025
2024
2023
平均
一般方式
10.0
7.1
7.0
7.43
英語4技能利用
8.2
7.1
7.5
7.60
学部平均(単純) 8.20 7.10 7.25 7.51
一般方式:倍率スコア 3.75
英語4技能利用:4.14
両方式とも倍率スコアが低く、統計的には不利 な状況です。
文学部の競合
競合スコア:両方式 6.83 (高め)。同日競合の影響で受験層が割れやすい配置です。この競合効果により、実質的な競争率がある程度緩和される傾向にあります。
文学部の難易度
一般方式:難度スコア 6.62
英語4技能利用:6.28
どちらも標準帯。国語・英語の二輪で”取り切る”設計 が有効で、深い読解力と論理的な記述力が求められます。
文学部のメリット・デメリット
文学部のメリット
競合が強い ことで、日程の組み方次第で上振れが期待できる過去問研究 が比較的効きやすい
文学部のデメリット
倍率の重さ が常にネック要約の精度不足で安定しない ケースが多い
学部代表(一般方式)総合指数:4.94 (倍率 3.75/難度 6.62/競合 6.83)
英語4技能利用:総合 5.11(倍率 4.14/難度 6.28/競合 6.83)
早稲田で受かりやすい9位 商学部
商学部は総合指数4.07 (数学型が学部内最高)で早稲田大学内で9番目に合格しやすい学部 です。競合がゼロ で、外的な追い風がなく、純粋な実力勝負 となる学部です。数学型と地歴・公民型で大きく状況が異なります。
商学部の倍率
学部平均の実質倍率:約8.0倍 (2方式平均)。数学型は6.5倍、地歴・公民型は9.5倍と、方式によって大きな差があります。
最新3年の実質倍率
学科・方式
2025
2024
2023
平均
数学型
6.8
6.5
6.2
6.50
地歴・公民型
10.3
9.3
8.9
9.50
学部平均(単純) 8.55 7.90 7.55 8.00
数学型:倍率スコア 6.11 … セット内では相対的に有利。統計上はやや有利。
地歴・公民型:倍率スコア 2.78 … セット最下位水準。実質倍率9.5倍は早稲田大学内で最も高く、統計上はかなり不利。
商学部の競合
数学型/地歴・公民型ともに 競合スコア:0.00 。同日競合による受験層の流出効果がほぼ働かないため、当日の自力勝負 になりやすい構造です。他大学との日程重複が少なく、商学部を志望する受験生が集中しやすい傾向にあります。
商学部の難易度
数学型:難度スコア 2.00 … 非常に難しい (計算+論理の精度要求が高い)。数学の力が合否を大きく左右します。
地歴・公民型:難度スコア 3.20 … 難しい 。暗記+精選演習で積み上げ可能ですが、高倍率との戦いが課題です。
早稲田商学部の数学はものすごく難しい です。
近年も平均点が低水準で推移しており、2025年度は60点満点中の平均が10.737点 という厳しい結果となっています。
商学部数学の難易度
早稲田大学「2025年度 一般選抜 学部別得点状況」によると、商学部(数学型)の数学の平均点は10.737/60点 でした。文系数学としては極めて高難度 です。
※出典:早稲田大学「2025年度 一般選抜 学部別得点状況」(2024年10月時点)
数学が得意ならぜひ望んでみると良い でしょう。
【早稲田大学商学部|英語】各設問の徹底対策とおすすめ参考書 早稲田大学商学部【数学】|本番で圧勝の徹底対策シリーズ
一方で地歴型 は、現在早稲田大学で一番難しくなっている形式 です。
倍率10倍を超えてくると、、1点,2点で合格が分かれてしまいます。
とはいえ、問題自体は基礎的な問題も多いので、基礎の徹底をしていただくことで現役生であっても合格することは可能 です。
英語のレベルはここ数年でものすごく上がっているので受験する人は要注意です。
商学部のメリット・デメリット
商学部のメリット
数学型 :数学が明確な武器なら差別化しやすい /得点設計がはまりやすい地歴・公民型 :難度は標準帯。範囲を絞った重点暗記+過去問反復 で伸ばせる英語は概ね標準~やや密度高めで、精度重視の学習 が結果に直結
商学部のデメリット
競合がゼロ で外的な追い風がなく、取りこぼしがそのまま致命傷 になりやすい数学型 :処理速度×正確性の両立が必須。苦手だと一気に厳しい 地歴・公民型 :倍率の不利が大きく 、統計上は分が悪い(過去問適合が鍵)
方式別・総合指数:
数学型:総合 4.23(倍率 4.86/難度 6.57/競合 0.00)
地歴・公民型:総合 3.39(倍率 3.29/難度 7.05/競合 0.00)
学部代表(ランキング表での表示)は数学型(総合 4.23)ですが、地歴・公民型も上記の通り数値を併記します。地歴・公民型は実質倍率9.5倍と早稲田大学内で最も高く、最も合格が難しい方式 となっています。
早稲田で受かりやすい10位 社会科学部
社会科学部は総合指数3.94 で早稲田大学内で10番目に合格しやすい学部 です。倍率は中程度ですが、競合がゼロ で外的な追い風がなく、純粋な実力勝負 となる学部です。
社会科学部の倍率
最新3年の実質倍率
学科・方式
2025
2024
2023
平均
社会科学部
5.0
8.5
8.0
7.17
倍率スコア:4.81 。実質倍率は中程度で推移していますが、倍率面での大きな優位性はありません。
社会科学部の競合
競合スコア:0.00 。同日競合による受験層の流出効果がほぼ働かないため、当日の自力勝負 になりやすい構造です。
社会科学部の難易度
難度スコア:3.71 (標準)。学際的な問題が特徴で、複数分野にまたがる知識と論理的思考力 が求められます。
社会科学部のメリット・デメリット
社会科学部のメリット
学際的な視点 を持つ受験生には適合しやすい過去問研究 で出題傾向を掴みやすい
社会科学部のデメリット
競合がゼロ で外的な追い風がない複数分野の知識が必要で対策範囲が広い
総合指数:3.63 (倍率 4.81/難度 3.71/競合 0.00)
結局、早稲田を受けるにはどの学部が良いの?
総合指数に基づく合格しやすさのランキングは以下の通りです。
学部単位での受かりやすさランキング(各学部の最高学科基準)
国際教養学部 (総合指数 8.56)スポーツ科学部 (総合指数 6.62)法学部 (総合指数 6.51)政治経済学部 (総合指数 6.49)教育学部 (総合指数 6.31)人間科学部 (総合指数 6.26)文化構想学部 (総合指数 5.21)文学部 (総合指数 5.11)商学部 (総合指数 4.23)社会科学部 (総合指数 3.63)
※総合指数は各学部内の最高スコアの学科・方式を基準としています。
※表の1-23位は学科・方式別の詳細ランキングです。学部内の全学科を確認することをお勧めします。
問題のレベル、倍率、競合を総合的に考慮すると、このような順番になります。
もちろん、入りやすい=簡単に入れるという意味ではありません 。
最初の段階でも述べていますが、絶対的な基礎学力は必要不可欠 です。基礎学力がまだまだないな・・・という人で、どうしても早稲田大学に入りたい!という人は、とにかくまずは基礎学力をつけることを意識 してください。
早稲田に受かるには結局どうしたら良いのか?
早稲田に受かるためには、文系、理系に関わらず英語をできるようにするのが最優先事項 です。
下記各学部ごとの、一般入試における配点と英語の配点割合を見てください。
注意事項
*政治経済学部:公式では「共通テスト100点+総合問題100点=計200点」と発表されており、総合問題内の英語比率は公表されていません。
*商学部:英語の配点は地歴・公民型と数学型で異なります。
*教育学部:学科によって配点が異なるため、志望学科の詳細を必ず確認してください。
※出典:早稲田大学「2025年度 一般選抜 学部別得点状況」および各学部公式ページ(2024年10月時点)
どこの学部も英語の配点が高く、早稲田大学全体だと約38% となります。早稲田大学の英語はどの学部も非常に難しく、そう簡単には対策は終わりません。
学力にもよりますが、1年単位での対策が必要 になってくる場合も多々あります。
チェック
当塾では、英語が全然できない基礎レベルから早稲田レベルまで、何をどのように勉強したら良いのか指導 をしていきます。もちろん、他の科目についても対策をしています。お気軽にご相談ください。
絶対に早稲田に合格したいなら英語を強化しよう!
絶対に早稲田大学に合格したい!という強い意志を持っているのであれば、下記をペースメーカー、目標にすると良いでしょう。
高校1年 →英検2級高校2年 →英検準1級高校3年 →英検1級単語
英語をどのように勉強したら良いのかわからない、参考書はどのような教材を使えば良いのか???という人は下記をご覧ください。
0から早慶に合格するための英語参考書 英語の読解の勉強法
早慶合格までの時間は具体的にどれくらい?
どれくらい勉強したら早慶に受かるのかわからない・・・
早慶合格までに必要な勉強時間について、偏差値別の学習時間の目安と効率的な時間配分 を具体的に解説しています。自分に必要な勉強時間を知りたい方は必見です。
[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/keio/sokei-studytime/"]
慶應にも受かりやすい学部はあるの
慶應にも合格するための穴場学部はありますよ
慶應義塾大学の穴場学部について、倍率・競合・難易度を総合的に分析したランキング を公開しています。慶應も併願したい方は必ずチェックしてください。
[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/keio/keio-ukariyasui/"]
早稲田・慶應の穴場学部を包括的に比較分析 した記事です。両大学を横断して最も合格しやすい学部を知りたい方は必見です。
[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/column/sokei-anaba/"]
GMARCHでも狙い目の学部はありますか?
GMARCHの方が学部が豊富で狙い目となる学部があります。
ただし、年によって狙い目、穴場の学部は異なりますので注意 してください。
GMARCH(学習院・明治・青山・立教・中央・法政)の穴場学部について、最新の倍率データと併願戦略 を詳しく解説しています。併願校選びで悩んでいる方は必見です。
[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/gmarch/ukariyasui-gmarch/"]
近年の受験は複雑になっているので、自分自身でも情報を仕入れていくのが必要不可欠です。
受験日程から考える入試戦略
受験を考える上で入試日程を熟知した上で、自身の受験校を決めることは必要不可欠 です。
どのような関係性になっているのか、難関大学の2月のスケジュールから考えていきます。
2月の入試日程を完全網羅し、早慶・MARCH・国公立の併願パターンと戦略的な受験スケジュール を詳しく解説しています。日程を最適化して合格率を上げたい方は必見です。
[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/2jukenschedule/"]
絶対に早稲田に合格したい方へ
どの学部を狙えばいいか戦略が立てられない 勉強しているのに成績が上がらない 早稲田の入試問題が難しすぎて手が出ない 自分の偏差値で本当に合格できるのか不安
その気持ち、よく分かります
多くの受験生が、同じ悩みを抱えています。
しかし、正しい戦略と適切な指導があれば、偏差値50からでも、偏差値40からでも、早稲田合格は十分に可能 です。
早稲田専門塾「ヒロアカ」の合格メソッド
当塾「ヒロアカ」では、早稲田大学専門塾として、一人ひとりに最適化された合格戦略で早稲田合格へと導きます 。
ヒロアカが考える早慶の合格までの道筋を知りたい方は、
今すぐ行動すべき理由
受験まで残された時間は限られています。
1日でも早くスタートすることで、合格の可能性は確実に高まります 。
特に、現在の偏差値が志望校に届いていない場合、今すぐ正しい戦略で勉強を始めることが不可欠 です。
まずはLINEで気軽に相談してみませんか?
お申し込みは簡単です。下記のボタンから、お気軽にお問い合わせください。
データソースと参照情報
本記事で使用したデータと出典
実質倍率データ :早稲田大学入学センター公表の「2025年度/2024年度/2023年度 一般選抜 入試結果」を基に算出。各学部・方式別の志願者数・受験者数・合格者数・実質倍率を使用。配点・試験構成データ :早稲田大学「2025年度 一般選抜 学部別得点状況」および各学部公式ページを参照。入試日程 :早稲田大学・慶應義塾大学・MARCH各大学の「2025年度 入学試験日程」を基に競合スコアを算出。難度評価 :過去問分析、大手予備校(河合塾・駿台・代ゼミ)の難易度評価、および当塾の指導実績を総合的に評価。教育学部英語の長文化 :河合塾「入試動向分析」、駿台「大学入試分析」(2022-2024年度)を参照。
入試制度・試験日程・配点は年度により変更される可能性 があります。出願時は必ず最新の入試要項 をご確認ください。
本記事のランキングは統計的な「合格しやすさ」を示すものであり、個々の受験生の得意・不得意科目、学習到達度によって実際の合格可能性は大きく変わります 。
「穴場学部」とは「簡単に合格できる」という意味ではありません 。どの学部も早稲田大学の高い水準の学力が求められます。
本記事の信頼性について
本記事は、早稲田大学が公式に発表したデータを基に、当塾「ヒロアカ」の豊富な指導経験にて作成しています。
すべてのスコア算出方法を公開し、透明性と再現性 を重視しています。
年度更新を継続的に行い、常に最新の情報を提供 することをお約束します。