2025年5月3日〜2025年5月5日に春期合宿(2泊3日)を開催しました。

本合宿の目的
ただ漠然と勉強をしても成績を上げることはできません。
成績を上げるためには、「考えて勉強をする必要がある。」という考えのもと、
生徒自身が考えて勉強ができるように指導をしていきました。
実施内容
勉強ができるようになるためには、学習を上手にできるかどうかが鍵になります。
多くの生徒は勉強をしたふりばかりで、勉強ができていません。
これまでの指導経験から、学習をどのようにしたら良いのか?を今一度確認するために
本合宿を実施していきました。
具体的には、勉強の仕方、取り組みの仕方、どのようにしたら成果を上げることができるのかといった、
勉強のOSの部分の指示をしていきました。
春合宿の実施スケジュール
| 時間 | |
|---|---|
| 5:30 | 起床 |
| 6:10 | 勉強開始 |
| 8:10 | 朝食 |
| 9:10 | 勉強 |
| 12:30 | 昼食 |
| 13:15 | 勉強 |
| 18:30 | 夕食 |
| 19:00 | 勉強 |
| 23:10 | 入浴 |
| 23:45 | 就寝 |
合計約30時間にわたって、学習時間と勉強の仕方をレクチャーしました。
春合宿での学習の仕方を一部紹介!
実施したスライドの一部をお伝えしていきます。
勉強ができるようになる子とできない子では、勉強の考え方・取り組み方が全く異なります。
これを知らずして、いつまでたっても勉強ができるようにはなりません。
そのため、当塾ではこのような勉強の根本原則、根本原理を春合宿の段階で落とし込んでいって、夏合宿までに実践をしていってもらっています。



日々の学習効果を最大化するために、
原点ノートという考え方を紹介し、日々実践するためにはどのようにしたら良いのか、
合宿で実践しました。
春合宿前と後で勉強への取り組み方が大きく変わりました!
![]()
生徒の振り返りの内容の一部を紹介!
1日目、2日目と注意をし続けた結果最終日には、
下記のように具体的に振り返りを書けるようになる生徒が多発しました。
言語力の差によって、まだまだ差はありますが、
「なぜできないのか?」の抽出をできる生徒ができるようになったのは、よかったです。
学力チェックの実施事項
各科目(英語中心)でどのような点をチェックしていったのかを見ていきます。
英語の学力チェック
この段階でできてないなければいけないことは、
文構造の基本を身につけていくことです。
普段の授業や自学習で行なっていることができてるかどうかを確認していきました。
1000問ほどのオリジナル問題を使って確認をしていきました。
どれだけできている生徒であっても、
文構造が取れてないと早慶の問題で高得点を取ることはできません。
この春の段階で徹底的に基礎を固めていきます。
学力チェックは、
文構造等といった構造的な部分だけでなく内容が取れるかについても行いました。
河合塾(当塾での受講推奨模試)の模試が近いこともあり、
形式を似せた問題にて、内容が取れているかどうかを確認しましました。
とはいえ、基礎がまだまだ不十分な生徒は(共通テストで50点以下)
模試をやってもただやるだけになってしまうので、
そのような生徒は、基礎学習を600問ほど行いました。
英語を読む上で主語が取れるかどうか?というのは、
非常に重要な要因であり、
英語ができない生徒はどこが主語なのか?というのがわかりません。
この基礎学習にて主語の特定をできるようにしていきました。
英語の集中講義
英語の個別講義では、クラスを分けて文章同士のつながりがどのようになっているのかを理解してもらっていきました。
- ing/thatの識別
- 等位接続詞
- 代名詞
- 論理構造の考え方
- 【何からはじめたらいい?という人向け】
【まず始めることをお伝えします】 - 早慶に合格するための戦略とは?
合格するための戦略とは? - 【高1】早慶現役合格の勉強法を徹底解説
志望校に合格するためにやるべきこと紹介 - 【高2】現役で早慶GMARCHに合格
必要な勉強法(勉強時間、参考書)を紹介 - 【高2】早慶絶対合格!!のためにすること
勉強時間、スケジュール、参考書、勉強法の紹介 - 早慶満点者インタビュー
早慶圧勝のために具体的に何をしたら良いのか
早慶対策に特化した塾を検討している場合は、早慶専門塾ヒロアカの無料受験相談を活用してみてください。現状の学力や志望学部に合わせて、具体的な勉強方針をアドバイスいたします。
また、LINEでもカウンセリングのお問い合わせができますので、LINEから気軽に申込たい場合は、以下よりお申込みください。
その他の科目について・・・
文系は国語、理系は数学を実施しました。
どのくらいの進度で進む必要があるのか、ポイントとなる問題を再度確認しました。
まとめ
毎年伝えていますが、、 早慶に合格するためには、盤石な基礎学力が必要不可欠です。
その必要性に再度気が付いていただけたようで何よりです。
受験生に必要なのは、新しい勉強法ではありません。
これまで自身が行ってきたことを信じて、 なんどもなんども基礎を繰り返すことが合格への近道となります。
また、本ブログを見て興味を持った学生、親御さんは、ご連絡いただければと思います。 お気軽にこちらよりご連絡ください。

















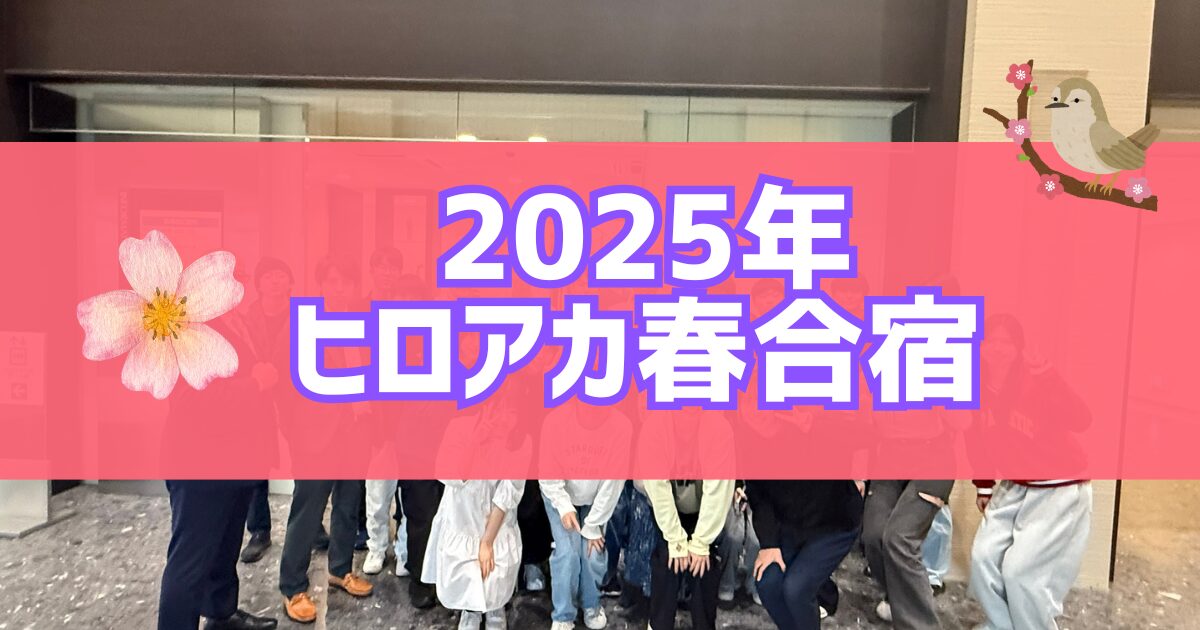
Published by