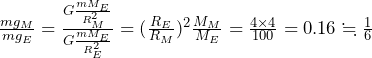まず、N=24について考えてみます。 N=24=で、約数をすべて列挙すると、{1,2,3,4,6,8,12,24}で約数の個数は、8コで約数すべての和は60です。 次に、N=24・3=72について考えてみます。 N=で、約数をすべて列挙すると、{1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,7
- …続きを読む
- まず、N=24について考えてみます。
N=24=
 で、約数をすべて列挙すると、{1,2,3,4,6,8,12,24}で約数の個数は、8コで約数すべての和は60です。
で、約数をすべて列挙すると、{1,2,3,4,6,8,12,24}で約数の個数は、8コで約数すべての和は60です。次に、N=24・3=72について考えてみます。
N=
 で、約数をすべて列挙すると、{1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,72}で約数の個数は、12コで、約数のすべての和は195です。
で、約数をすべて列挙すると、{1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,72}で約数の個数は、12コで、約数のすべての和は195です。これら3つから、約数の個数と約数のすべての和について考えてみます。
・N=24のとき、{1,2,3,
 ,
, ,
, ,
, ,
, }で、
}で、 は、1,3
は、1,3 は2,
は2,
 は
は ,
,
 は
は ,
, に含まれていることが分かります。
に含まれていることが分かります。つまり、
 (0≦k≦3)は3の約数(1,3)とすべてかけられています。
(0≦k≦3)は3の約数(1,3)とすべてかけられています。逆に、
 は1,2,
は1,2, ,
,
 は3,
は3, ,
, ,
, に含まれていますから、
に含まれていますから、 (0≦l≦1)は2の約数(1,2,
(0≦l≦1)は2の約数(1,2, ,
, )とすべてかけられています。
)とすべてかけられています。以上から約数の個数はN=
 のべき乗部分に注目して、(1+3)(1+1)=4・2=8コと求められます。
のべき乗部分に注目して、(1+3)(1+1)=4・2=8コと求められます。和は、
 となります。
となります。・N=72=
 のとき、{1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,72}
のとき、{1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,72}つまり、{1,2,3,
 }
}_(傍線部)はN=24に含まれなかった約数です。_(傍線部)も

すべてかけられているので先程と同様に考えると、(1+3)(1+1+1)=(1+3)(1+2)=4・3=12コで、和は です。
です。■JMO(日本数学オリンピック)の予選の問題ですが、約数の個数という面で楽しんで頂けないでしょうか?
結局、
 をm=10,
をm=10, (1≦i≦m)として、重複を2で割ったのが本問でした。
(1≦i≦m)として、重複を2で割ったのが本問でした。ここまでくれば、アルゴリズムが見えてきますね。
 (1≦k≦m)を素数として、
(1≦k≦m)を素数として、 と表されたNの約数の個数は、
と表されたNの約数の個数は、
約数の総和は、
 と一般化できます。
と一般化できます。さて、小手調べに以下の問題にとりくんでみよう!
▶問1
ある整数の約数をすべて足すと168になり、約数の逆数をすべて足すと、2.8になる整数を求めよ。(有名問題)
解
 とする。
とする。

∴N=60…(答え)
■多項式と関係が深いです
ただの丸暗記だと、上の式変形は難しいかもしれませんが、この記事を読んだ皆さんなら、簡単に解けたのではないでしょうか?
▶問2
正の整数の組み(a,b)であって、a<b,ab=29!を満たし、かつaとbが互いに素であるようなものはいくつあるか。(2017JMO 予選2)
解 29以下の素数は、{1,2,3,5,7,11,13,17,23,29}の10コである。
まず、a=bと仮定すると,ab=29!⇄
 =29!=28!・29で、29の要素は1つしかなく、平方数にならない。よって、a≠bである。
=29!=28!・29で、29の要素は1つしかなく、平方数にならない。よって、a≠bである。29!=
 とする。
とする。 =x+y(1≦i≦10)、(1≦x≦
=x+y(1≦i≦10)、(1≦x≦ )として、たとえばaが
)として、たとえばaが 、bが
、bが を因数にもって、aとbが互いに素に矛盾するから、aとbは一方が
を因数にもって、aとbが互いに素に矛盾するから、aとbは一方が をもつかどうかしかありえず、これは2通りである。
をもつかどうかしかありえず、これは2通りである。各
 (1≦i≦10)について同じことがいえるので、
(1≦i≦10)について同じことがいえるので、 通りだが、これにはa>bも含まれている。
通りだが、これにはa>bも含まれている。対称性(aとbをいれかえても変わらない)より、a<bとa>bの個数は同じだから求める個数は
 通り…(答)
通り…(答)







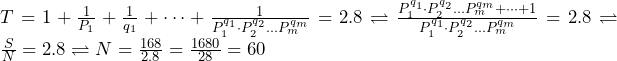
















 図2
図2