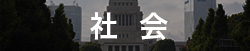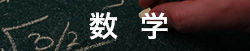慶應義塾大学商学部の英語対策
慶應商学部英語で9割を取れる!完全攻略の勉強法がここにある
慶應商学部英語で高得点を取りたいあなたに朗報です。
このブログ記事では、慶應商学部英語で9割という高得点を取るための勉強法を徹底解説します。
慶應商学部英語の各設問を完全攻略。
- 長文読解
- 空欄補充
- 文法問題
慶應商学部の合格のカギは英語力。
ここで紹介する勉強法とおすすめの参考書を駆使して、
慶應商学部英語を完全攻略していきましょう!
[toc]
慶應商学部英語の全体概観|傾向
まずは、慶應商学部の問題の全体像を見ていきましょう。
慶應商学部の問題の大問ごとの文字数と傾向です。
文字数は、昨今の平均値で例年文字数は変わるので注意してください。
大体、平均すると800~900words程度になっています。
| 大問 |
種類 |
語数 |
| Ⅰ |
長文問題 |
約900words |
| Ⅱ |
長文問題 |
約900words |
| Ⅲ |
長文問題 |
約900words |
| Ⅳ |
文法問題 |
|
| Ⅴ |
空欄補充 |
約1000words |
| Ⅵ |
長文内容一致 |
150~200Words |
| Ⅶ |
語形変化(動詞) |
150~200Words |
| Ⅷ |
語形変化(名詞) |
150~200Words |
英語重視で独特な問題の多い慶應義塾大学の中では珍しく標準的な問題が出題されます。
問題は全編を通して、
早慶を目指すのであれば標準レベルの問題となっていますが、、
問題数が多く最初は解き切るのが大変です。
一問一問の慶應義塾大学のその他の学部と比べると高くはありません。
ただし、問題の量が例年大問7,8まであるので処理速度を上げていかなければ対応ができません。
速読力は必須!
慶應商学部に合格したいのであれば、全てを時間内に解き切るための速読力は必須です。
どのような形で速読すれば良いのか、練習方法はこの記事で説明していきます。
[word_balloon id="1" balloon="line" name_position="under_avatar" name="ブタトン" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="false" avatar_hide="false" box_center="false" font_size="17" name_color="#10193a" position="R" bg_color="#8de055" font_color="#fff"]受験者皆ができる!と思う問題が多いですが、それを時間内に正確に解く力となると、多くの受験生が困ってしまいますね。[/word_balloon]
慶應商の英語は何点取れれば良いのか?
結論から言うと、慶應商学部の英語の得点は、
- 200点中150~160点(75%~80%)取れるようにしてください。
*A方式で英語が苦手であれば、120~130点程度でも良いです。
慶應商学部は、早慶の中でも高得点争いをすることが多いです。
なぜそれだけの点数を取らなくてはいけないのかを、合格最低点と平均点から考えていきましょう。
慶應商の合格最低点
慶應商学部はA方式とB方式でわかれており、方式によって難易度が全然違います。
B方式の場合は非常に得点率が高くなってくるので要注意してくださいね。
詳しくはこちらの記事で紹介しています。
[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/column/sokei-anaba/"]
慶應商A方式での科目と配点
英語:200点
地歴:100点
数学:100点
英語は200点と全体の半分を占めています。
A方式の場合は、全体で60%前後の点数を取ることができれば良いので、
英語で9割取ることができたら、合格はかなり可能性が高いです。
| 年度 |
配点 |
合格最低点 |
得点率 |
| 2023 |
400 |
237 |
59.3% |
| 2022 |
400 |
240 |
60.0% |
| 2021 |
400 |
252 |
63.0% |
| 2020 |
400 |
244 |
61.0% |
慶應商B方式での科目と配点
英語:200点
地歴:100点
論文:100点
一方でB方式の場合は、必要な点数が7割ほどになるので、
英語は最低8割はほしく社会でも9割近くの高得点が求められます。
| 年度 |
配点 |
合格最低点 |
得点率 |
| 2023 |
400 |
278 |
69.5% |
| 2022 |
400 |
302 |
75.5% |
| 2021 |
400 |
288 |
72.0% |
| 2020 |
400 |
309 |
77.3% |
慶應商学部の英語の平均点
| 年度 |
英語
[200] |
得点率 |
| 2023 |
110.21 |
55.1% |
| 2022 |
109.24 |
54.6% |
| 2021 |
100.35 |
50.2% |
| 2020 |
124.55 |
62.3% |
| 2019 |
115.24 |
57.6% |
| 2018 |
124.95 |
62.5% |
全体で見ると大体120~125点(60%)程度は、平均的に取れています。
注意!
2021年度は少し難しかったですが、合格最低点を見るとそこまで、
下がってないことから合格者は難しくても同じ程度の点数をとっていることがわかります。
合格した塾生も同じような傾向でした。
社会が簡単で9割近くは取れるのが普通なので、英語でも点数が取れることが求められます。
慶應商英語の設問ごとの配点予想
全体的に早慶標準的な問題が出題されます。
一つ一つの問題はそこまで難しくなく、
早慶の中では最も簡単な学部(Marchよりも簡単かも?)の一つです。
ですが、全体で80%程度取らないと合格は難しいので、
そういったことを考えると、
かなり難しい学部(さすが慶應)となるのです。
| 大問 |
種類 |
難易度 |
配点 |
| I |
長文問題 |
★★★ |
38 |
| II |
長文問題 |
★★★ |
36 |
| III |
長文問題 |
★★★ |
38 |
| IV |
文法問題 |
★★ |
21 |
| V |
空欄補充 |
★★ |
18 |
| VI |
長文内容一致 |
★★★★ |
16 |
| VII |
語形変化(動詞) |
★★★ |
15 |
| VIII |
語形変化(名詞) |
★★★ |
18 |
7,8のみ記述形式の問題になります。
長文については下記のように計算しました。
|
空欄補充 |
推論orテーマ |
内容一致 |
全体合計 |
| 問題数 |
3or4 |
0or1 |
6 |
|
| 点数 |
3 |
5 |
4 |
|
| 合計 |
9 or 12 |
5 |
24 |
36 or 38 |
慶應商の英語は空所補充が合格の鍵
慶應商学部では様々な形式の空所補充が出題されます。
空所補充の問題数は?
大問1~3の空欄補充(10問)→30点
大問5(6問)→18点
大問7(5問)→15点
大問8(6問)→18点
合計81点(全体の40%)が空欄補充問題です。
すなわち、空所補充が苦手=不合格ということになります。
慶應商学部に合格したいのであれば、空所補充の対策は徹底的に行うべきです。
どのように空所補充に立ち向かうのか?
- 慶應商学部の空所補充問題ですが、対策の方法はいろいろあるのですが、一番重要視してほしいことは、文法的に解くと言う視点を忘れないと言うことです。
- ついつい、内容的に考えてしまうことも多いのですが、早慶の空所補充は文法、表現、コロケーション的なつながりで問題を解くこともしばしばあります。
慶應商の英語の時間配分
慶應商学部の問題を解くときの理想的な時間配分です。
| 大問 |
種類 |
時間配分 |
| I |
長文問題 |
17分 |
| II |
長文問題 |
17分 |
| III |
長文問題 |
17分 |
| IV |
文法問題 |
5分 |
| V |
空欄補充 |
5分 |
| VI |
長文内容一致 |
7分 |
| VII |
語形変化(動詞) |
5分 |
| VIII |
語形変化(名詞) |
5分 |
とはいえ、大問1~3を17分で解けるようになるのは至難の業です。
日頃から速読、スキャニングを瞬時にできるように訓練を積んでおいてください。
慶應商学部の設問別の対策・勉強法
それでは、ここからは、
長文問題の読解、それぞれの問題に対しての対策をお伝えいたします。
[word_balloon id="1" position="L" size="M" balloon="line" name_position="under_avatar" radius="radius_12" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="true" font_color="#ffffff" bg_color="#70a6ff" font_size="22" balloon_full_width="true"]慶應商学部に合格するためにどのように問題を解いたら良いのかを教えていきますね![/word_balloon]
【大問1,2,3】|長文問題の対策
3つの長文の語数を合わせると2500~3000words程度になり、
これを先ほどの時間で行うことを考えると、
とにかく時間との戦いになってくることがわかります。
もちろん、速読=闇雲に抽出して読んでいくというわけではありません。
筆者の主張、設問形式に合わせて緩急をつけて読んでいくことが必要です。
読解時に具体⇔抽象の関係を常に頭にいれて、
「今この部分は筆者の論理の中ではどこに当てはまるのか?」を確認しておきましょう。
この理解が素早く早くできる=具体的な部分を飛ばして読んでも文章の論理を追うことができるので、
速読が可能となっていきます。
長文問題で出題される問題のタイプは下記ようなものが想定されます。
- 空欄補充
- 内容一致/不一致
- タイトル問題
- 推論問題
- 下線部言い換え
それでは、設問別で具体的に見ていきましょう。
【慶應商/英語長文】空欄補充問題の対策
空欄補充問題を解くポイントは、
- 空欄部分が文章内の他の部分でどのようにいいかえがなされているか
を発見できるかと言うのが結構大きいいです。
もちろん、
文章は1パラグラフ内で1つだけしか言いたいことはありません。
ということは、空欄部分もパラグラフ内の他の部分で違う言葉で言い換えられていることがわかります。
この言い換えに気づくことができるかどうかがポイントです。
文章を構文や単語レベルで読むのではなくて、
論理的に読む練習をどれだけ積んできたかが空欄補充のポイントになります。
論理的に読むメリット
- 当塾では論理的に文章を読む練習をしていくので、こうした空欄補充が苦手になるということがありません。
【慶應商/英語長文】タイトル問題の対策
まずこのタイトルではどのようなことを見抜く必要があるでしょうか?
それは、パラグラフ毎の筆者の主張を見抜いて、それがすなわちどういうことをいっているかを見抜く訓練が必要です。
部分の内容ではなくて、
文章全体に貫かれる筆者の主張がどのようなものなのかを理解できる能力が求められています。
タイトル問題では?
部分の理解ではなく、文章全体での筆者の主張を見ていく必要がある。点数も高いと予想されるので、必ず取れるようになりたい設問。
【英語長文】内容一致or不一致問題の対策
長文問題の出題形式では最もシンプルな形式です。
選択肢を見て本文で言及されていたかそうでないかを確認するというだけです。
この問題の解答のポイントは、
選択肢と長文内でのそのいいかえにきづくことができるかということです。
多くの正誤問題は長文の内容をそのままの形で選択肢にでてきません。
名詞構文に変えてみたり、動詞、因果関係、主語を変えてみたり、さまざまな表現でパラフレーズ(いいかえ)を行なっています。
このパラフレーズに気づくための語彙力をつけているかどうかが早慶合格には必須。
過去の慶應商学部のテーマ一覧
[su_spoiler title="クリックで表示。ネタバレ防止のため隠しています" icon="plus-square-2"]
2021年 「Gene Sperling」「新しい経済指標の必要性」「ダーウィン思想の影響」
2020年 「米大統領小伝」「よい議論の仕方」「利潤追求と企業 倫理」
2019年 「19世紀の工場労 働者」「都市再編の問題」「良い指導者に求 められるもの」
2018年「技術革新と豊かさ」「「労働形態の変化と 職場の人間関係」「循環型経済と持続 可能社会」
2017年「中国の Alibaba」「SNS とコミニュケ ーション」「綿産業の歴史」
2016年「休暇の過ごし方」「脳にまつわる誤解」「社会的持続可能性」
2015年「労働時間短縮と 創出される余暇」「環境問題と消費行動」「トリクルダウンと VS トリクルアップ」
2014年「ソーシャルネットワーク今昔」「ネットショッピングと幸福感」「経済指標だけでは見えないもの」
2013年「企業の問題解決プロセス」 「「米国とインドの社会変化」「「米国における社会的地位と収入」 」
2012年「オーストラリアの二酸化炭素対策」 「欧米の自動車規制」「道徳的価値観」
2011年「テレビ・ゲームの効用」「タイの風習」「環境問題と企業努力」
2010年「ビジネス界のcreativity」「「アジアの社会保障制度」「多様性の有益生」「新聞への投書記事」
2009年「人間の危機意識の起源」「ベンチャービジネス」「インドの意外な携帯電話事情」「中国旅紀行」[/su_spoiler]
長文のテーマはビジネス、経済関連の話題が多いですね。
SNSなどベンチャービジネスなど最新のワードがでてきているので、こうした話題に疎い人は過去問で演習を積むのと同時に過去問にでてきた重要な概念をまとめておく必要があります。
普段からTech系の記事を読んだり、海外の新聞を読んでいるとこうした文章を読むのが速くなるでしょう。
【慶應商/英語長文】頻出の出典を見てみよう!
[word_balloon id="1" position="L" size="M" balloon="line" name_position="under_avatar" radius="radius_12" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="true" font_color="#ffffff" bg_color="#70a6ff" font_size="22" balloon_full_width="true"]ここでは慶應商学部でよく出る出典から、何個か紹介していきますね![/word_balloon]
せっかくスマートフォンを使っているのであれば、海外の記事を読んでみましょう。
早慶の文章は新聞記事から出題されることも多いので、読んでおくことで同じような記事に出くわすことは高いです。
特に慶應商学部は問題自体は難しくないですが、問題文が多いのでいかに普段から長文に読み慣れているかどうかというのが合否を決めています。
ぜひ読んでみてください。
Techcrunch
全世界でトップ500に入る巨大メディアです。多岐に渡るジャンルを扱っているにも関わらず、非常に見やすいデザインで、自分が読みたい記事を探しやすいのも好印象です。日本語版もあるので読み比べても面白いかと思います。
Mashable
Mashableはスタートしたソーシャルメディアや、ガジェット、アプリ、さらにエンターテイメントなどのニュースを配信するメディアで2005年に創設されました。social medhia 、Techというカテゴリがあるのでコツコツと読んでおくと良いでしょう。
Freaknomics
かつて出版されたFreaknomicsという本の著者のブログ。かつて日本でも「ヤバい経済学」として出版されていました。
直接的な受験対策にはならないかもですが、
雑学として読んでみても良いと思います。
[itemlink post_id="18105"]
【大問4】文法問題の対策
標準的な文法問題です。
まれに難しい文法、語法が問われますが、消去法で解くことが可能です。
基本的な語彙と文構造を見破れるかどうかを見ています。
早慶に合格するのであれば全問正解することが望まれます。
【大問5】空欄補充問題の対策
100語程度の長文を読んで、その空欄にあてはまる単語を選択肢から選ぶ問題です。
上記の空欄補充の解き方にもある通り、
1パラグラフ1メッセージ原則がわかっていれば容易に解ける問題です。
自分の知っている表現にすることを目的にするのではなくて、
文章上の論理から何を言っているのか?、
本文内で空欄部といいかえられている部分はどこか?を厳密に考えて解いてください。
【大問6】内容一致問題の対策
大問6を見ると、4つの英文が出てきます。それぞれの英文は数行あり、どれも内容をちゃんと理解することが求められます。具体的には、次のような質問が出題されることが多いです:
特に難しい形式の質問は出てこないのですが、推論問題が少し難しいです。
選択肢をしっかりと比べて考えるのに時間がかかるかもしれません。
勉強の段階でしっかりと英文を読解するスキルを鍛えて、
答えるスピードを上げる訓練が大切です。
【大問7,8】語形変化(記述)の対策
150字程度の文章を読んで動詞を変化させて、
文章の空白部分を埋めるタイプの問題です。
文章構造を素早く見ぬき、どんな品詞が入るのかを考えて選択肢の形を変えていく必要があります。
例えば、「He __ to school。」という文があり、
選択肢として「go」が与えられた場合、
適切な形に変えて「goes」と答えるような問題です。
大問7,8で形式が違うので具体的に見ていきます。
動詞の語形変化問題
基本的には、
文章構造を素早く見ぬいて、どのような形にするのが良いのかを考える癖をつけてください。
注意!
動詞の活用が重要で、現在分詞、過去分詞、三単現のsが問われます!
日頃から気をつけましょう。
名詞への語形変化
記述形式です。150字程度の文章を読んで動詞を名詞化し、空欄に適切な語彙を入れる問題です。
普段から単語帳を覚える際に類義語を意識して覚えておく必要があります。
動詞を名詞化した単語を覚える際には、
語源の知識が役に立つので興味のある人は調べてみてください。
接頭辞、接尾辞とは?
generation の -ation, beautiful, wonderful の -ful のような単語の末尾の,単語の一部分。
名詞化されるということ以外は普通の空欄補充と解き方は変わりません。
[word_balloon id="1" position="L" size="M" balloon="line" name_position="under_avatar" radius="radius_12" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="true" font_color="#ffffff" bg_color="#70a6ff" font_size="22" balloon_full_width="true"]慶應の理工学部でも同じような問題が出題されるので、過去問がなくなってしまった人は理工学部もみてみてくださいね[/word_balloon]
[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/taisaku/keio/rikou/kriko-english/"]
慶應商学部の英語の短文要旨選択問題の対策
12年から16年まで出題されていた問題です。
ここ2年は出題されていませんが、対策をしておく必要があるでしょう。この問題は筆者の主張が読めているかどうかを確認するための問題です。
対策として
普段から文章を読みながら要約を書き文章内で筆者の主張は何なのか?ということに重きをおいて読解を進めていくことが肝心です。要旨=本文内で言及されていることと同じではないことに注意してください。
本文内の枝葉、すなわち具体例部分や例外事項の部分で説明されていることは要旨には含まれません。
[word_balloon id="1" position="L" size="M" balloon="line" name_position="under_avatar" radius="radius_12" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="true" font_color="#ffffff" bg_color="#70a6ff" font_size="22" balloon_full_width="true"]どの文章が、筆者の主張になるのか?というのは一日二日で身につくものではありません。
早い段階から要約で要旨を把握する訓練をつけておくことをおすすめします。[/word_balloon]
【慶應商英語】で9割取るためには?
ここまでお伝えした内容でも過去問で実践したら、
十分に慶應商学部で9割取れるようになる知識は身につきましたが、
普段の勉強でどのようなことをしたら良いのかをお伝えしてきます。
ここまで見てきたように慶應商学部では全体的にスピードが重要になります。
慶應商学部の問題をスピード感を持って解くことができるためには、下記5つの力が重要になります。
- 英検準1級レベルまでの語彙力を正確に
- 熟語・文法・語法の知識を正確に
- 構文把握を正確に
- 読解スピードをWPM150目安
- 問題の該当箇所を正確に認識する
1,英検準1級レベルまでの語彙力を正確に
慶應商学部は早慶標準レベルの英検準1級レベルまでの語彙力が求められます。
読解時にはどの単語も正確に出るようにしていきましょう。
下記順序でやっていくのがおすすめです。
語彙問題対策で書けるように
- シス単レベルまでは、動詞を見たら名詞、形容詞形、名詞を見たら形容詞、動詞形をいえるようにしていきましょう。
2,熟語・文法・語法の知識を正確に
「早慶には文法はでないから、やらなくても良い!!」
と言うのは聞いたことありませんか?
確かに共通テストを中心に大学入試は長文中心になっていますが、
慶應商学部ではそれは当てはまりません。
全編を通して文法の学力が求められています。
「大学受験スーパーゼミ 全解説 頻出英文法・語法問題 1000」や「Dual Effect」あたりの教材を
一冊完璧にしておくのと、熟語をマスターしてください。
3,構文把握を正確に
大問7,8の語形変化の問題は、語彙力がもちろん必要ですが、
何の品詞を入れたら良いのか?を確定するためには、
構文把握力が必要不可欠となります。
おすすめは「英文熟考」ですが、
それ以外にも早慶レベルで使用できる構文についてはこちらで抜粋していますので確認してください。
[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/eigo/sokei-englishinterpretation/"]
4,読解スピードをWPM150目安
慶應商学部に合格するためには、読解スピードが150程度は必要です。
WPM150というと一般的な大学受験生の倍くらいのスピードになります。
このスピードを出すためには単に読んだり、音読をしているだけではできるようになりません。
【練習1】スラッシュリーディング
英文を読む際にペースが遅いと感じる人は、スラッシュ・リーディングの技法を習得すると良いでしょう。
この技法をマスターすることで、読解スピードを大幅にアップさせることが可能です。
スラッシュ・リーディングとは、英文を意味のまとまり、つまり句や節単位で分けて読む方法です。
これにより、文章の流れや意味をスムーズにつかむことができます。
Given the unpredictable weather conditions / in the coastal regions, / it’s essential / to always carry an umbrella / when heading outdoors.
このような少し難しい英文でも、「沿岸地域の予測不可能な天候を考慮して、/ 屋外に出るときは / 必ず / 傘を持参する / ことが必要です」というように、まとまりごとに翻訳することで理解を深めることができます。
文章を読む際に、このように句や節をイメージしながら読む練習を続けると、英文読解のスキルが向上します。
「レベル別英語長文LR」や「ハイパートレーニング」といった教材はこのあたりの配慮がされた形になっているのでおすすめです。
【練習2】音声を使ったシャドーリーディング
高速の音声を聞きながら、
それに合わせて読むことでその速さに引っ張られて文章を読む練習を積むことで、
読むスピードが徐々に速くなってきます。
読むのが遅い原因は、前から順番に処理が遅いのが大きな原因の一つです。
そのため、高速な音声をつかって練習を積むことで強制的に前から処理ができる練習を積むことができます。
「ぐんぐん読める英語長文」は長文自体の解説が現段階で最も詳しいので、
こちらの教材をやっていくと良いでしょう。
【練習3】フラッシュリーディング
フラッシュリーディングと言われてもわからない人が多いと思うので、
こちらの動画を見てください。
こちらの方法まで取り組めば、かなりのレベルまで鍛えることが可能です。
アプリでもでているので、上記二つの練習に飽きたら使ってみると良いでしょう。
5,問題の該当箇所を正確に認識する
単に速く読んでいたとしても、
設問と関係ないところを読んでいても試験においては意味がありません。
慶應商学部ではさまざまな問題形式があるので、
問題形式に合わせて瞬時に文章の読み方を変えるようにしていきましょう。
問題演習の練習用としては下記のような教材がおすすめです。
- 早慶の過去問
- The Rules3,4
- やっておきたい英語長文500~700
- ポラリス英語長文3
- レベル別英語長文5,6
[keio]
慶應義塾大学商学部に圧倒的な実力で合格できる専門対策をします
まずは資料請求・お問い合わせ・学習相談から!
早慶専門個別指導塾HIRO ACADEMIAには、慶應義塾大学専門として商学部への圧倒的な合格ノウハウがございます。
慶應大学商学部に合格するためにどのよう勉強をしたらよいのかを指示する学習カウンセリングも承っています。
学習状況を伺った上で、残りの期間でどう受かるかを提案いたしますので、ぜひお気軽にお電話いただければと思います。
⇒ 慶應義塾大学商学部に合格したい方は、まずは当塾のカウンセリングにてお問合せください!