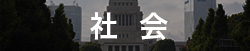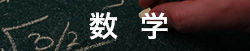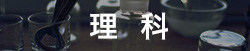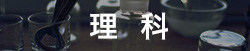慶應義塾大学医学部
 4.5
4.5
[toc]
全体概観:配点150点 時間100分
例年大問が4題で、質量共に最高峰の入試が続いている。試験時間に対して量が膨大であるため、どれだけ取れるかが肝心となります。
また典型問題の暗記では太刀打ちできないのはもちろんのこと、すべての範囲において深い理解が求められる。
出題範囲・頻出分野
慶應医学部の数学は、数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学Bからの出題となります。
大問1は小問集合で、大問2が確率、大問3がベクトル、座標、微積、大問4が微積という出題が続いていきます。
記述量もバラバラであり、全体的に質が高く、穴埋めだからといって答えだけが簡単に出る出題もなく、高い数学力が求められています。
日頃からどのように対策をしていくか
中途半端な理解力では太刀打ちのできない慶應医学部の入試問題ですが、問題を解けている人も事実です。
数学を圧倒的に得意科目にして慶應医学部で合格レベルの答案を書くために日頃どのような対策をしていけばよいのか、以下お伝えしていきます。
基礎の深い理解を
慶應医学部の数学は、チャートやfocus goldといった網羅系の問題集を暗記した付け焼き刃の数学力では太刀打ちできません。
思考力、空間把握能力、幾何的センス、記述力など多方面の高度な数学力が要求されます。
問題数をこなすことはもちろん大事ですが、そうしたことだけに固執するのではなく、自分の頭でじっくり考え抜き、しっかり理解することが肝心です。
*上記、幾何的センスと述べていますが、センスは考えることで養われるものです。センス=生まれつき持ったものと考えずに自身の覚えた知識をもとに考える癖をつけましょう。
強靭な計算力を養う
すべての問題で高い計算力を求められる慶医数学において短時間で正確に答えを合わせる処理力は必須となります。
計算問題を疎かにして、入試に望む人が非常に多いです。
焦りが加わった土壇場で合否を分けるのは、思考力ではなく、計算力だということは頭に入れて下さい。
おすすめとしては、一日15~30分でも十分です。その時間で積分の難しい計算を行ってみてください。
おすすめの教材としては、『合格る計算Ⅲ』です。
積分練習カードというランダムで積分ができるカードが付属しているので行ってみて下さい。
合格る計算の詳しい使い方はコチラから
頻出の分野は確実に得点していく
慶医は大問1が比較的取り組みやすい小問集合、大問2が慶医花形の確率漸化式、大問3,4が微積、空間、座標などの医学部らしい系統の出題と傾向に変わりありません。
大問3,4は難しい問題が多く、最後までたどり着くのは困難な問題が多いためそこまで差はつきません。
大問1は確実に得点するとして、近年取り組みやすくなっている大問2の確率漸化式の出来は合否に大きく関わるので、完答しておきたいです。
圧勝している人はこう考える!
では、慶医の確率漸化の中でも簡単めの2016年の大問2を見てみましょう。
「問題を貼る」
まず、問題の操作がわかりにくいため、図におこしてみます(図1)
このように操作が込み入っている問題では、状態を図にすると、すごく考えやすくなります。
特に図2のように状態を点、操作を辺で表したグラフを状態偏移グラフといいます。
さてさっそく問題を解いていきたいと思いますが、以下では記述にも対応できるように記述式で書いていきます。
 =
= …①
…①
 =
= …②
…②
 =
= …③
…③
…(答)
またPはAorBorCのいずれかにいるので =1…④(n≧2)も成り立ちます。
=1…④(n≧2)も成り立ちます。
(2)②より、 =
= =
= より、
より、 =
= …②’で③②から、
…②’で③②から、 =
= ⇆
⇆ =
=
 は1つおきに等比数列となりますから
は1つおきに等比数列となりますから


が分かり、 =1,
=1, =0,
=0, =0,
=0, ,
, ,
, =0を代入して
=0を代入して

 …(答)となります。
…(答)となります。
あとは②に代入すれば、
 …(答)も求まります。
…(答)も求まります。
(3)いきなり、 :「操作Tをn回繰り返し終えたとき、初めてPがCにいる確率」とかいわれてもよく分からないので、こういうときはとりあえず実験あるのみです。
:「操作Tをn回繰り返し終えたとき、初めてPがCにいる確率」とかいわれてもよく分からないので、こういうときはとりあえず実験あるのみです。
実験・n=4ではA→A→A→B→C、A→A→B→B→C、A→B→B→B→C の3通り。
・n=5ではA→A→A→A→B→C、A→A→A→B→B→C、A→A→B→B→B→C、A→B→B→B→B→C の4通り。
ここら辺で、”PはBに進むとAには戻れず、Bに留まるかCに進むかの2択”しかないことの意味が浮き彫りになってきます。
A→B、B→B、B→Cの確率は全て で、A→…A→B…→B→Cでn-1コの→のうち、どこでA→Bにきりかわるかで、(n-1)通りなので、
で、A→…A→B…→B→Cでn-1コの→のうち、どこでA→Bにきりかわるかで、(n-1)通りなので、 …(答)
…(答)
(4) :(ⅰ)n回終えたときに点PがAorBにいる。(ⅱ)それまでに1回だけ頂点Cにいた。
:(ⅰ)n回終えたときに点PがAorBにいる。(ⅱ)それまでに1回だけ頂点Cにいた。
前問(3)に(ⅱ)の状況が似ていますから、(3)を利用してみます。今回はn回目にPがCにいないので、一般的に操作K回後にCがいたとします。その確率は(3)より (2≦K≦n-1)です。
(2≦K≦n-1)です。
・ について。K+1回の操作後から、Aにずっといるので、
について。K+1回の操作後から、Aにずっといるので、
・ について。(3)の実験から分かるようにi回の操作Tをほどこして、Bにいる確率は
について。(3)の実験から分かるようにi回の操作Tをほどこして、Bにいる確率は なので、
なので、 {n-(k+1)}
{n-(k+1)}
 と
と は互いに排反なので、
は互いに排反なので、 ・1・{
・1・{ =
= (n-K)(K-1)=
(n-K)(K-1)= {(n+1)K-
{(n+1)K- -n}=
-n}= {
{ }=
}= {
{ }=
}= …(答)が求まります。
…(答)が求まります。
■(4)の別解について、場合分けの基準は(4)に沿うものとします。B→C→Aは1かたまりで、Cをただの通過点とみなして、全事象を としても一般性を失いません。
としても一般性を失いません。
(ⅰ)のとき、n-1回の移動のうちどこがA→B,B→Aになるかの組み合わせを考えると 通り
通り
(ⅱ)のとき、n-1回の移動のうち、どこがA→B、B→A、A→Bになるかの組み合わせを考えて、 通り
通り
(ⅰ)(ⅱ)より =
= =
= …(答)としても求められますね!
…(答)としても求められますね!
状態遷移グラフを用いた問題で、もう少し難し目の出題が2014年度の慶医にあるので是非自分で挑戦してみよう!