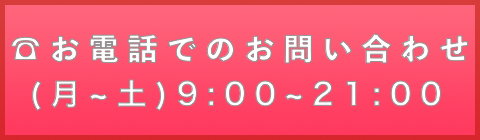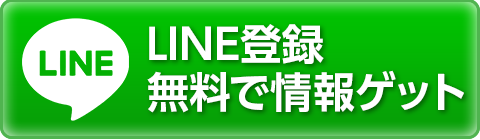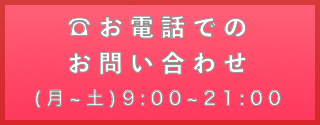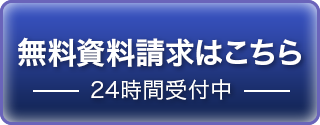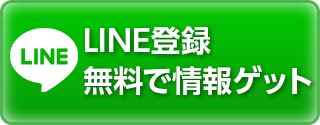ページ目次参考書の特色使い方1ランク成績を上げるための使い方この参考書によくある質問集 参考書の特色 ▶対象者 一通り応用問題も解き終えて入試数学で点数を稼げるようになりたい方(偏差値65以上の方) 「1対1」や、「青チャート」などの問題集が解けている状態の人向けの問題集です。タイトル
- …続きを読む
- [toc]
参考書の特色
▶対象者
一通り応用問題も解き終えて入試数学で点数を稼げるようになりたい方(偏差値65以上の方)「1対1」や、「青チャート」などの問題集が解けている状態の人向けの問題集です。タイトルに「やさしい」と書いてありますが、そのタイトルに惑わされて早い段階で使用しても無駄になってしまうくらいレベルが高いです。この問題集を仕上げれば十分に難関大学の問題に対応できる力がつきます。数学を入試の得点源にしたい人にとっても申し分のない問題集です。ただし、基本的には早慶理工の入試であってもこのレベルまで行う必要がないことが多いです。特に現役生であれば1対1を完璧に理解してその後、理科、英語に時間を使うほうが有効でしょう。受験は一科目の勝負ではなく総合力の勝負です。
例題50問、演習題150問の計200問が、15章に振り分けられた構成となっています。各例題には「考え方」の部分で解法のヒントがワンポイントで解説されています。また、例題・演習題ともに別解が豊富ですので、多面的な考え方を身につけることができます。
使い方
▶おすすめ使用期間
1ヶ月半~2ヶ月
難関大学に向けた仕上げの段階で使用する問題集です。取り組む際には、時間の上限を決めて(長くても30分程度)、入試を意識して取り組みましょう。入試は1問あたりにかけられる時間が限られていますから、解ける問題を多く解くことが大事となります。ある程度考えて解けなければ、解答を見て解法を理解するのも大事です。また、自力で最後まで解けた人もそうでない人も、別解がある問題については別解を読みましょう。この問題集は別解が豊富なので、自身の方針でできなかった場合についても「なぜできなかったのか?」、できた場合でも他の解答を見て「なぜこの解答方針でできたのか?」を多面的に考えていきましょう。問題への多面的なアプローチを学ぶことで、自分の今の解法よりも短時間で解ける解法を学ぶこともできますし、他の問題にも応用できる解法を学ぶこともできます。
ここで注意したいのは、全ての問題を完璧にする必要はないということです。この問題集に取り組むレベルであれば、1対1シリーズで扱うような典型問題はできているはずで、また時期としても受験勉強も佳境である秋くらいになっていると思います。上述しましたが、そのレベルであれば大半の大学の数学で合格レベルの点数を取ることができます。数学でそれ以上を目指すのではなく、他の科目も完璧にしていくことで確実な合格を目指しましょう。
時間がなければまず例題のみを1周、もしくは*印(難問についているマーク)の問題を除いて1周するとよいでしょう。もちろん解答・解説、別解はじっくり読むことが大切です。例題のみを2周、3周することでも力がつきます。もちろん、2周目、3周目で演習問題にも取り組むことができればなおよいです。1ランク成績を上げるための使い方
この問題集に取り組む時期ですと、自分でもう一度解くべき問題、そうでない問題を自分で見極めて問題を解く時期だと思います。具体的には、初見で解けた問題や、初見で解けなくとも解答を理解でき、2周目で再現できた問題など、ある程度理解できている問題が出てくると思います。もう一度解くべき問題にはチェックを入れ、そうでない問題は2周目は解答を流し読みするなど、勉強の仕方にも工夫をしていきましょう。
この参考書によくある質問集
[speech_bubble type="ln-flat" subtype="L1" icon="seitom5.gif" name="質問1"]この問題集を使用したら入試の過去問に取り組んでも大丈夫ですか?[/speech_bubble][speech_bubble type="ln-flat" subtype="R1" icon="platon1.jpg" name="プラトン先生"]同じ河合出版の問題集で、さらにハイレベルな問題集として「ハイレベル理系数学」というものがありますが、基本的には「やさしい理系数学」を解くことができれば難関校対策として十分です。このレベルの問題集が解ければ、さらにレベルを高めるよりも他の科目の点数を上げていく方が効率がいい場合が多いです。ですので、入試の過去問演習により本番に慣れる練習をした方がいいでしょう。[/speech_bubble][speech_bubble type="ln-flat" subtype="L1" icon="seitow3.gif" name="質問2"]すべての問題の解法を理解する必要はありますか?[/speech_bubble][speech_bubble type="ln-flat" subtype="R1" icon="platon1.jpg" name="プラトン先生"]上述しましたが、すべての問題を理解できればそれに越したことはありません。ですが、この問題集は網羅系の問題集ではなく、過去問に取り組む前の仕上げの問題集であるので、1問1問をしっかり理解することが大事になります。ですので、すべての問題を理解しようとして全体がおろそかになってしまうよりは、例題のみをしっかり理解した方が効果が上がります。また、1回の演習で完璧にする必要もありません。1周目で完璧に理解できなくとも、時間をおいてもう1回解いた時により理解できていることもあります。1周目で完璧にしようとして時間をかけるよりも、繰り返して理解する方がより効果が上がります。[/speech_bubble]▶数学の最速の対策はこちら!
https://hiroacademia.jpn.com/program/sugaku-benkyo/









 解答は
解答は