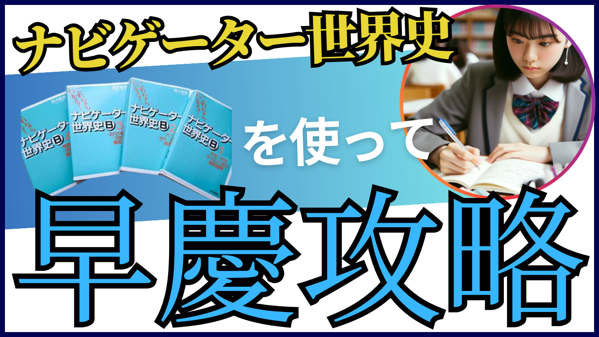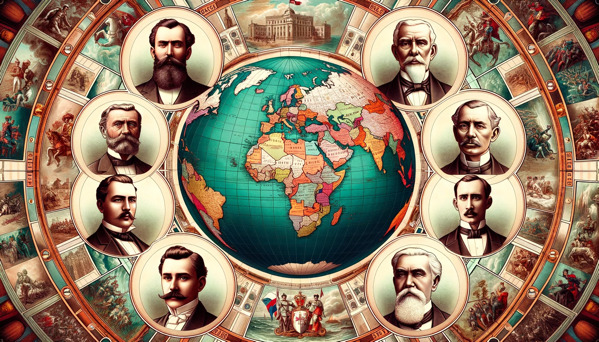早稲田大学商学部【日本史】対策・勉強法
商学部の日本史入試は、他学部に比べて難易度は高くありませんが、
[toc]
早稲田大学商学部【日本史】の傾向
早稲田大学商学部の日本史入試は、60分で大問6題の構成となっています。
第1問は古代史(マーク式)
第2問は中世史(マーク式)
第3問は近世史(マーク式)
第4問と第5問は近代史(マーク式+記述式)
第6問は現代史(記述式+論述式)
近代史と現代史の出題比率が高く、合わせて全体の5-6割を占めています。
問題数は58-60問程度で、正誤判定問題の比重が高くなる傾向にあります。
早稲田大学商学部【日本史】の特徴
商学部の日本史入試には以下の特徴があります。
正誤判定問題が多い
史料問題が頻出する
近現代史からの出題が多い
短文論述問題が必ず出題される
早稲田大学商学部の日本史入試は、全時代から均等に出題されるのが特徴です。
例えば2019年の入試を見てみると、第1問が古代、第2問が中世、第3問が近世、第4問と第5問が近代、第6問が現代と、古代から現代までバランスよく出題されていました。
もう一つの特徴は、正誤判定問題の比重が高いことです。
史料問題が必ず1題以上出題されるのも特徴です。
毎回必ず20字程度の短文論述問題が1題以上出題されているのも大きな特徴といえます。
早稲田大学商学部【日本史】への取り組み
商学部日本史入試対策の取り組み方は以下の通りです。
基礎知識をしっかり定着させる
過去問顒題で正誤判定に慣れる
史料問題対策を継続的に行う
近現代史を重点的に学習する
日頃から論述の訓練をする
まず基礎知識は教科書を丁寧に読み、年表や重要語句を繰り返しノートに書き写すことで定着させましょう。参考書の一問一答形式の問題集で知識を定期的に確認し、弱点を克服していきましょう。特に「2つ選べ」の難しい正誤問題には注意しましょう。
史料問題対策は、教科書や参考書の史料を繰り返し読み、
未知の史料が出ても対応できるよう、読解力を鍛える必要があります。
近現代史は出題範囲が広いため、経済・産業・金融分野を中心にその時代背景を意識しながら学習しましょう。関連するニュースなどにも日頃から興味を持つことが大切です。
論述対策は、限られた字数で主要点をまとめる訓練を日頃から欠かさず行うことが肝心です。
早稲田レベルまでの日本史の学習の仕方についてこちらから確認ください。
早稲田大学商学部【日本史】対策1:史料問題対策
史料問題対策としては、教科書や参考書に掲載されている有名な史料を中心に学習し、その史料から求められる背景知識を身につける。
史料問題には、既に知っている有名な史料と、これまで見たことがない未知の史料の2種類があります。
資料|既知の史料対策
既知の史料対策としては、教科書や参考書に掲載されている「日葡辞書」「異国船渡来之図」「徽廬詩文集」などの有名史料を繰り返し読み込み、その内容と歴史的背景を関連付けて理解することが重要です。
例えば、過去問で出題された「日葡辞書」に関する設問は、当時の南蛮貿易やキリシタンの状況について問われることが多いので、そうした背景知識を身につける必要があります。
既知資料の方が細かいことが問われて難しいことが多いので、既知資料は必ず覚えておくようにしてください。
資料|未知の史料対策
一方、未知の史料については、与えられた資料から時代背景を読み取る訓練が必要です。
未知の史料であっても、資料から時代の特徴を推測する力が問われるのです。
早稲田大学商学部【日本史】対策2:論述問題対策
早稲田大学商学部の日本史では例年、単文論述問題と語句問題が出題されます。
語句問題の対策
語句問題というのは歴史用語を覚えているかどうかの確認です。一般的に私立大学の問題だと空欄補充があっても選択肢から選ぶタイプが多いため、実際に書けるかどうかというと微妙な人が多いです。勘違いをしてしまってはいけないのはいきなり全ての歴史単語を覚えようとしてしまうことです。これでは通史を勉強するために莫大な時間がかかってしまいます。まずは通史を確実に理解できるようになった段階でその後に実際に歴史用語が書けるかどうかの確認をしていきましょう。論理的な意味がわからない単語を人は覚えることができません。歴史用語が通史の中のどの地点に位置するのかを理解できるレベルになった段階で用語を覚えていくことで効率よく歴史用語を確認することができます。
論述対策
論述問題対策の具体的な方法は以下の通りです。
その上で、過去問題を利用して、20字程度の限定された字数で的確に主要点をまとめる練習を繰り返し行う。
例えば「日清戦争」のキーワードが与えられた場合、戦争の原因や結果、影響を端的にまとめられるよう訓練する。採点基準を意識し、主要点を絞ることもポイント。
私大志望の多くの学生は論述問題をしていないことが多いため、この論述問題が合否の分かれ目になるでしょう。
特に因果関係、相関関係は日本史のすべての範囲で理解できていないとまず早稲田大学商学部での合格は難しいでしょう。
1つ例を見てみましょう。
日本史の問題じゃないじゃん
と思うかもしれませんが、このように日本史を覚えるだけでなく理解していることが必要なのです。
不況の時どのようなことが起こるのか、ということについてはこの時代のことだけではありません。わからなかったら解答をみてよく理解しましょう。
解答例を挙げてみたいと思います。
失業者の増加や雇用不安の高まりで、消費が落込み不況が進んだ。(30字)
早稲田大学商学部【日本史】対策3:現代史・近現代史対策
近現代史の対象となる年代は、おおむね次の通りです。
近代史:幕末から第二次世界大戦まで
現代史:第二次世界大戦後から現在まで
特に現代史は出題範囲が広く、背景知識が求められます。
教科書の近現代史部分を丁寧に読み込み、基礎を固める
新聞やニュースで経済や産業関連の話題に関心を持つ
参考書で近現代史を補完学習し、理解を深める
関連する文献や資料を読んで知識を広げる
近現代史の対策では、経済・産業・金融分野を中心に学習することが重要です。
例えば、過去の入試では高度経済成長期の経済政策に関する設問が次のように出題されています。
「高度経済成長を実現するため、高度技術産業の育成と生産性の向上が計られた。その一環として、産業の高度化をはかる目的で1961年に制定された政策法は何か。」
この設問では、高度経済成長期における産業高度化政策としての「技術開発促進法」について答える必要があります。
このように、近現代史の分野では、単に年代や事項を丸暗記するだけでなく、なぜその政策が必要とされたのか、どのような経済状況を改善するためだったのか、その背景を理解することが求められます。
学部の性質上、戦後の経済分野もよく出題されています。この部分に弱い学生は対策をしておくべきでしょう。
早稲田大学商学部【日本史】で使える参考書
おすすめの参考書は以下の通り。
日本史B講義の実況中継の効果的な使い方はこちらから
[nlink url="https://hiroacademia.jpn.com/blog/sankosyo/nihonshi/ishikawajikkyo/"]