参考書の特色 対象者 整数問題の訓練をしたい人向け 本書を始めるにはまずセンター試験で8割以上取れる力は最低限必要です。 整数の分野は差のつく分野ではありますが、センター試験レベルで苦戦するのであればそちらの勉強をした方が費用対効果は高いです。高度な内容も含むので基礎力がないとまず挫折することになり
- …続きを読む
- [toc]
参考書の特色
対象者
整数問題の訓練をしたい人向け
本書を始めるにはまずセンター試験で8割以上取れる力は最低限必要です。
整数の分野は差のつく分野ではありますが、センター試験レベルで苦戦するのであればそちらの勉強をした方が費用対効果は高いです。高度な内容も含むので基礎力がないとまず挫折することになります。本書の内容は高校数学の集大成といえるでしょう。
整数問題でよく出るパターンはほぼ網羅されていますので本書を終えれば自信をもって数学の受験に臨めます。使い方
完成までの期間
1~2ヶ月程度
整数問題に取り組むのが初めてなら順番に進めましょう。既に多少できるのであれば苦手な分野のみに絞ったり、巻末の問題をいきなり解いていくやり方でも良いでしょう。
整数問題は大抵の場合最後に取り組むことになるので無理に全部をやる必要はありません。過去問をやる方を優先してください。








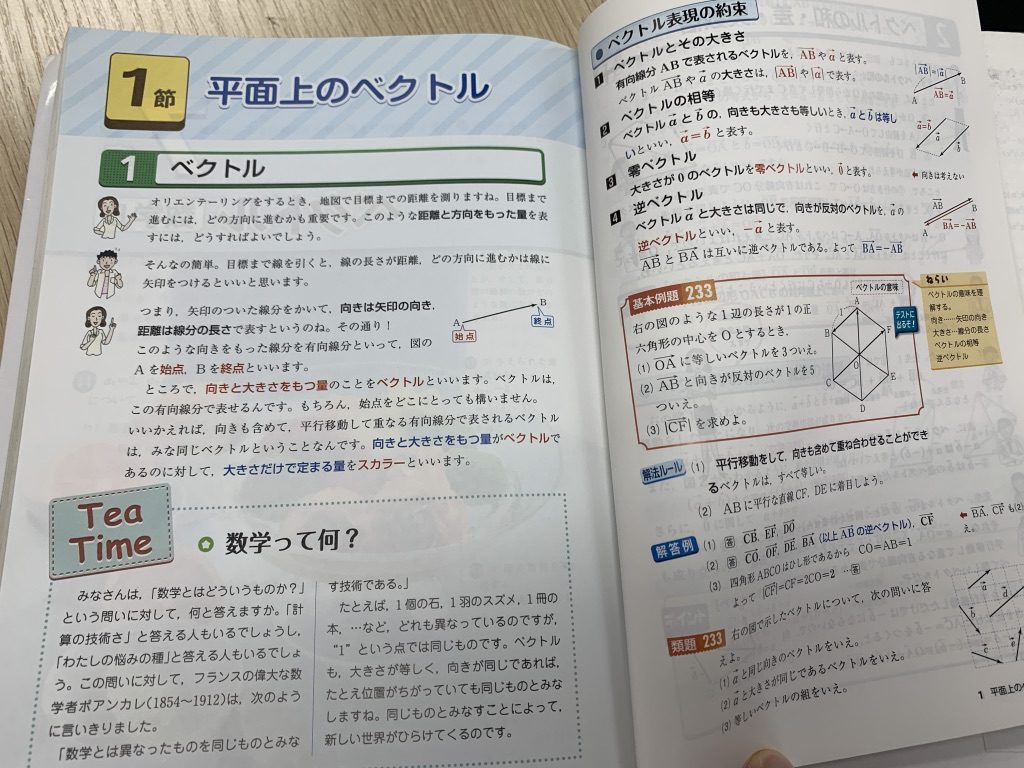
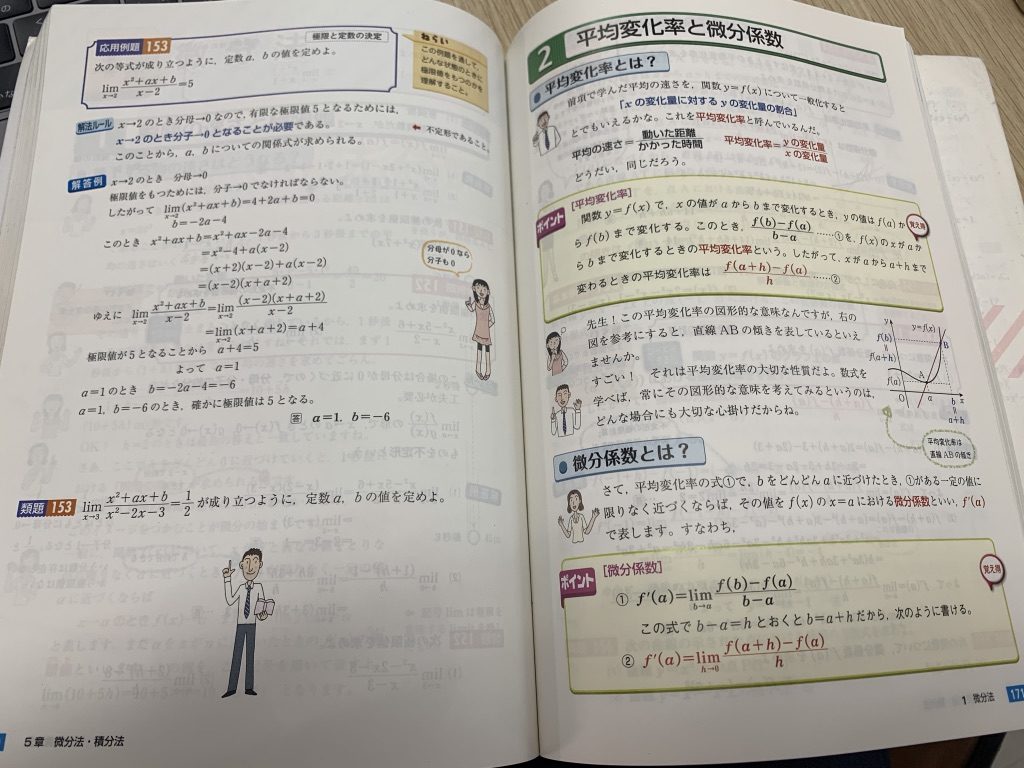


 解答は
解答は




